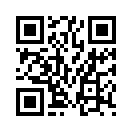2009年07月27日
1学期を終えて
1学期を終えて
1学期が終了し、子どもたちが成績表を持ってきました。中1生にしてみれば、初めての通知簿を見ることになります。当塾の今年の中1の子どもたちの特徴は、多くの生徒が英数で「5」をとり、理科・社会・国語も「5」が多かったことです。もちろん、中間テストや期末テストの点数が高かったことも大きな理由ですが、それ以上に、小学6年生から指導している「字をていねいに書くこと」「見やすいノート作り」「ノートまとめの仕方」「授業の聞き方」などを指導していたことが、とても大きかったように思います。
通知表は、学校のテストだけでなく、ノートまとめの仕方や、授業中の発表などの評価がとても大きなウエートを占めているため、塾の生徒たちは、そうしたところも普通にできるようになってきています。
特徴的な生徒の例で見てみましょう。
A君は、小学4年生くらいから塾で学んでくれている生徒さんですが、小学4〜5年のころは、ひたすら塾で絵や図を書いて解く、算数の文章題をし、思考力を高めてゆきました。さらに、小6では、中1の英語・数学を中心に予習し、同時に、字をていねいに書き、見やすいノートを作る、ノートのまとめ方、授業の聞き方をマスターしてゆきました。また、同時に毎回、本読みでさまざまな伝記に触れ、偉人の人生に憧れていたことや、毎回、感想文を書き続けてもらっていたこともとても大きかったように思います。
表面的には、私たちの塾の指導方針に従って頑張ったというだけのことでしょうが、もっと内面を見てゆくと、とても大きな成長をしてゆかれていることがわかります。
A君に対して、一番私たちが驚くのは、「びくともしない重心とひたむきさ、そして友達に対するやさしさ」です。友だち思いであることと、何事にも粘りがあること。こうした力を小学生の間にできるだけ育むことが、中学になって、大きく飛躍してゆくことにつながってゆくのではないかと思います。A君以外にも、こうした力を育んでいる子どもたちがたくさんいます。小学4年から6年までの過ごし方が、中学・高校でのライフスタイルに結ばれていることを感じてなりません。
1学期が終了し、子どもたちが成績表を持ってきました。中1生にしてみれば、初めての通知簿を見ることになります。当塾の今年の中1の子どもたちの特徴は、多くの生徒が英数で「5」をとり、理科・社会・国語も「5」が多かったことです。もちろん、中間テストや期末テストの点数が高かったことも大きな理由ですが、それ以上に、小学6年生から指導している「字をていねいに書くこと」「見やすいノート作り」「ノートまとめの仕方」「授業の聞き方」などを指導していたことが、とても大きかったように思います。
通知表は、学校のテストだけでなく、ノートまとめの仕方や、授業中の発表などの評価がとても大きなウエートを占めているため、塾の生徒たちは、そうしたところも普通にできるようになってきています。
特徴的な生徒の例で見てみましょう。
A君は、小学4年生くらいから塾で学んでくれている生徒さんですが、小学4〜5年のころは、ひたすら塾で絵や図を書いて解く、算数の文章題をし、思考力を高めてゆきました。さらに、小6では、中1の英語・数学を中心に予習し、同時に、字をていねいに書き、見やすいノートを作る、ノートのまとめ方、授業の聞き方をマスターしてゆきました。また、同時に毎回、本読みでさまざまな伝記に触れ、偉人の人生に憧れていたことや、毎回、感想文を書き続けてもらっていたこともとても大きかったように思います。
表面的には、私たちの塾の指導方針に従って頑張ったというだけのことでしょうが、もっと内面を見てゆくと、とても大きな成長をしてゆかれていることがわかります。
A君に対して、一番私たちが驚くのは、「びくともしない重心とひたむきさ、そして友達に対するやさしさ」です。友だち思いであることと、何事にも粘りがあること。こうした力を小学生の間にできるだけ育むことが、中学になって、大きく飛躍してゆくことにつながってゆくのではないかと思います。A君以外にも、こうした力を育んでいる子どもたちがたくさんいます。小学4年から6年までの過ごし方が、中学・高校でのライフスタイルに結ばれていることを感じてなりません。
2008年03月26日
子どもたちは、もともと深く考える力がある
子どもたちは、もともと深く考える力がある
先日、保護者懇談会で、小学生のAさんのお母さんに、最近はいかがですか?と尋ねると「成績が劇的にあがりました!」とおっしゃってくださいました。
塾に入ってすぐの1学期と2学期では、信じられないくらいの上がり方だったそうです。
テストもどの科目も100点ばかり取ってきて、一体どうしたの?と思うくらいだと言われていました。
塾の小学部では、学校で習うような予習や復習は一切していません。けれども、成績が上がってしまう。それも4科目全部が・・・。これが、一人や二人ではなく、ほとんどの生徒がその実感を持つのですから驚きです。
塾を設立した当初は、学校の予習や復習を中心に行なって、成績が伸びることは伸びるのですが、義務でやっているという感じでした。
しかしここ、数年前から、算数思考文章題への取り組みで、絵や図を書くだけで問題を解いてゆくようになったのではないかと思います。この算数思考文章題は、本当に不思議なほど深く考える思考力と算数の力、国語読解力がめきめきついていきます。
今は、子ども達が深く考えるようになって、「賢い子が生まれていっている」という感じでしょうか。結局、勉強の出発点は、「興味を持って学ぶ」「子どもたちは、もともと深く考える力がある」ということに気づくだけだったというのが、私の実感です。
先日、保護者懇談会で、小学生のAさんのお母さんに、最近はいかがですか?と尋ねると「成績が劇的にあがりました!」とおっしゃってくださいました。
塾に入ってすぐの1学期と2学期では、信じられないくらいの上がり方だったそうです。
テストもどの科目も100点ばかり取ってきて、一体どうしたの?と思うくらいだと言われていました。
塾の小学部では、学校で習うような予習や復習は一切していません。けれども、成績が上がってしまう。それも4科目全部が・・・。これが、一人や二人ではなく、ほとんどの生徒がその実感を持つのですから驚きです。
塾を設立した当初は、学校の予習や復習を中心に行なって、成績が伸びることは伸びるのですが、義務でやっているという感じでした。
しかしここ、数年前から、算数思考文章題への取り組みで、絵や図を書くだけで問題を解いてゆくようになったのではないかと思います。この算数思考文章題は、本当に不思議なほど深く考える思考力と算数の力、国語読解力がめきめきついていきます。
今は、子ども達が深く考えるようになって、「賢い子が生まれていっている」という感じでしょうか。結局、勉強の出発点は、「興味を持って学ぶ」「子どもたちは、もともと深く考える力がある」ということに気づくだけだったというのが、私の実感です。
2008年03月20日
毎日、子どもたちと出会う前に…
毎日、子どもたちと出会う前に……
私は、子ども達と出会う前、保護者の方と出会う前、いつも心がけていることがあります。それは、その子が持っている本来の可能性を、私はまだまだ見えていないだろうなということです。見えていないと思うことで、もっともっと探そう、引き出そうとします。けれども、教師の側が、限定してしまうと、生徒の側も、「自分なんてこんなもの」と限定してしまうのではないかと思うからです。だから、私は、認めてあげたいし、ほめてあげたい。そんな風に思っています。
私は、子ども達と出会う前、保護者の方と出会う前、いつも心がけていることがあります。それは、その子が持っている本来の可能性を、私はまだまだ見えていないだろうなということです。見えていないと思うことで、もっともっと探そう、引き出そうとします。けれども、教師の側が、限定してしまうと、生徒の側も、「自分なんてこんなもの」と限定してしまうのではないかと思うからです。だから、私は、認めてあげたいし、ほめてあげたい。そんな風に思っています。
2008年03月04日
伝記にハマル小学生クラス
伝記にハマル小学生クラス
当塾の小学生クラスでは、毎回5分から10分の読書の時間があります。この時、ほとんどの子ども達に好きな伝記を読んでもらっているのですが、本嫌いな子が、しばらくするとすごく好きになってきます。そして、とてもおもしろい傾向があることに最近気がつきました。
それは、普段のその子からはあまり想像がつきにくい「偉人」が好きになるのです。A君は「野口英世」でした。何度も何度も繰り返し読みたがり、家でもお母さんに買ってほしいと言われます。
Bさんは「リンカーン」でした。奴隷解放運動をするリンカーンにとても強く響くのです。家に帰ってからもその話をお母さんに詳しくされると言います。Cさんは「マザーテレサ」でした。毎回、ものすごく感動してやまないのです。E君は「宮沢賢治」でした。賢治のまっすぐな生き方にどうしても憧れてしまうようで、徐々に宮沢賢治のように勉強をしようと思い、ひたむきなE君が現れました。Fさんは「ジャンヌ・ダルク」でした。フランスを守ろうという壮絶な生き方に憧れます。G君は「ジョン万次郎」、H君は「アインシュタイン」「ニュートン」など科学者の生き方に憧れてなりません。
こうした伝記を読む中で、子どもたちは世界を視野に入れ始め、自分の人生を考え、試練や困難が来たときにどう乗り越えればよいのかと、先人の生き方から学んでいきます。それは、決して私達が教えられるものではなく、子ども達一人ひとりが発掘しているようなものです。しかし、だからこそ、個性があって、誰一人として同じ感じ方ではなく、その子にしかないものがあるのだと思えてなりません。
学びたい意欲は誰にもあります。そして、人生について、人間について、勉強の意味について、子どもたちはみんな知りたがっています。
私は、この伝記を読むことで、子どもたち自身の力でそうしたこともつかんでいってもらいたいと願っています。
当塾の小学生クラスでは、毎回5分から10分の読書の時間があります。この時、ほとんどの子ども達に好きな伝記を読んでもらっているのですが、本嫌いな子が、しばらくするとすごく好きになってきます。そして、とてもおもしろい傾向があることに最近気がつきました。
それは、普段のその子からはあまり想像がつきにくい「偉人」が好きになるのです。A君は「野口英世」でした。何度も何度も繰り返し読みたがり、家でもお母さんに買ってほしいと言われます。
Bさんは「リンカーン」でした。奴隷解放運動をするリンカーンにとても強く響くのです。家に帰ってからもその話をお母さんに詳しくされると言います。Cさんは「マザーテレサ」でした。毎回、ものすごく感動してやまないのです。E君は「宮沢賢治」でした。賢治のまっすぐな生き方にどうしても憧れてしまうようで、徐々に宮沢賢治のように勉強をしようと思い、ひたむきなE君が現れました。Fさんは「ジャンヌ・ダルク」でした。フランスを守ろうという壮絶な生き方に憧れます。G君は「ジョン万次郎」、H君は「アインシュタイン」「ニュートン」など科学者の生き方に憧れてなりません。
こうした伝記を読む中で、子どもたちは世界を視野に入れ始め、自分の人生を考え、試練や困難が来たときにどう乗り越えればよいのかと、先人の生き方から学んでいきます。それは、決して私達が教えられるものではなく、子ども達一人ひとりが発掘しているようなものです。しかし、だからこそ、個性があって、誰一人として同じ感じ方ではなく、その子にしかないものがあるのだと思えてなりません。
学びたい意欲は誰にもあります。そして、人生について、人間について、勉強の意味について、子どもたちはみんな知りたがっています。
私は、この伝記を読むことで、子どもたち自身の力でそうしたこともつかんでいってもらいたいと願っています。
2007年03月22日
テストの受けとめ方
B君が中1の時のことです。国語だけがどうしても点数が伸びないという悩みを抱えていました。B君に限らず、テストの点数が伸びずに悩む生徒は後を絶ちません。しかし、テストに対しての受けとめ方をもう一度見直してみたいと思いました。
B君に、国語のテスト結果を持ってきてもらい、学校のワークと出題範囲を見比べてもらうことにしました。学校の先生が出される出題範囲をどのくらい自分がカバーしていたのか、どのくらい前からテスト対策をやり始めていたのか、覚えるべきことを完璧になるまで覚えたのか、そういったことをチェックしてもらい、次のテストに向かう計画をその時に作ってもらうことにしました。次のテスト以降で結果が変わっていったのは言うまでもありませんでした。
このように、テストをやりっぱなしにして、振り返らないことは非常にもったいないことだと言えます。テストに限らず、私達の人生に降りかかる出来事のすべては、出来事が終わった後から次への挑戦が始まるのではないでしょうか。
テストの点数が良くても、「ああ、良かった。もう大丈夫」と思えば、そこで停滞してしまうかもしれません。点数が悪くても、本当にどこが足りなかったか、自分の結果をつぶさに検証し、改善点を見出してゆくならば、必ず半年、1年後には、大きな成長をしてゆくことは間違いないことだと思います。こうした人生の智慧ともいえるものを、勉強を通して身につけてゆくことを私たちは願っています。
B君に、国語のテスト結果を持ってきてもらい、学校のワークと出題範囲を見比べてもらうことにしました。学校の先生が出される出題範囲をどのくらい自分がカバーしていたのか、どのくらい前からテスト対策をやり始めていたのか、覚えるべきことを完璧になるまで覚えたのか、そういったことをチェックしてもらい、次のテストに向かう計画をその時に作ってもらうことにしました。次のテスト以降で結果が変わっていったのは言うまでもありませんでした。
このように、テストをやりっぱなしにして、振り返らないことは非常にもったいないことだと言えます。テストに限らず、私達の人生に降りかかる出来事のすべては、出来事が終わった後から次への挑戦が始まるのではないでしょうか。
テストの点数が良くても、「ああ、良かった。もう大丈夫」と思えば、そこで停滞してしまうかもしれません。点数が悪くても、本当にどこが足りなかったか、自分の結果をつぶさに検証し、改善点を見出してゆくならば、必ず半年、1年後には、大きな成長をしてゆくことは間違いないことだと思います。こうした人生の智慧ともいえるものを、勉強を通して身につけてゆくことを私たちは願っています。
2007年03月13日
子どもの可能性は無限大!…1
子どもの可能性は無限大!…1
小学2年A君の場合
A君は、まだ小学2年生。外遊びが大好きで、元気なお子さんでした。けれども、勉強面においては机の前でじっと座ることがまだ、難しいというお子さんでした。
この学年では60分座って勉強するのも、大変なことだと思います。特にA君にとっては、塾の習い始めは、きっと大きな試練だったのだと思います。算数の文章題も、読んでできない。国語の読解問題も、最後まで読めない。・・・うーん。どうしようか。と思い、計算のパズルをさせてみました。すると、もう夢中になって解きだすのです。私は、生き生きとパズルに取り組むA君に、他の一切の勉強をストップして、パズルに専念してもらいました。
計算パズルを宿題にもしてきていい?と聞くので、了承しました。
2カ月か3カ月、本当に計算パズルだけをやり続けました。パズルも徐々に難しくなってゆきだした頃、国語の読解問題を1枚渡しました。
すると、3カ月前には、文章を最後まで読むことができなかったA君が、最後まで読んで、解きだし、おまけに全問正解してしまったのです。
そこで、気をよくしたA君に、今度は学校準拠の国語の問題集を初めからするようにと手渡すと、喜んで国語をするようになりました。すると1カ月ほどで、問題集の半分を終えてしまいました。
そして、いよいよ本題の算数の文章題に取り組むように勧めると、かつて、字も汚かったA君が、すごくきれいな字で、文章題の絵や図を書いて、問題を解きだしたのです。これには、本当に驚きました。
そして、どんどん、算数の文章題を解きだすのです。そして。嬉しそうに「先生、これ、おもしろいわ」と言うのです。今度は、算数の文章題に夢中になり、一心不乱に勉強しています。今では90分を集中して、考え続けるA君に変身してしまいました。
私たちがA君に教えてもらったこと。それは、無理やりさせる勉強より、達成感や、喜びを持ちながら、「考えるって楽しい。」という気持ちで勉強に向かうと、本当に可能性が開かれてゆくということでした。
A君にとっては、外遊びも、パズルも、国語の読解問題も、算数の文章題も「外遊び」の延長線上に位置しているのかも知れません。創意工夫しながら夢中で遊ぶ子が、創意工夫して「深く考える」勉強につながるよう、子ども達を応援したいと思いました。
小学2年A君の場合
A君は、まだ小学2年生。外遊びが大好きで、元気なお子さんでした。けれども、勉強面においては机の前でじっと座ることがまだ、難しいというお子さんでした。
この学年では60分座って勉強するのも、大変なことだと思います。特にA君にとっては、塾の習い始めは、きっと大きな試練だったのだと思います。算数の文章題も、読んでできない。国語の読解問題も、最後まで読めない。・・・うーん。どうしようか。と思い、計算のパズルをさせてみました。すると、もう夢中になって解きだすのです。私は、生き生きとパズルに取り組むA君に、他の一切の勉強をストップして、パズルに専念してもらいました。
計算パズルを宿題にもしてきていい?と聞くので、了承しました。
2カ月か3カ月、本当に計算パズルだけをやり続けました。パズルも徐々に難しくなってゆきだした頃、国語の読解問題を1枚渡しました。
すると、3カ月前には、文章を最後まで読むことができなかったA君が、最後まで読んで、解きだし、おまけに全問正解してしまったのです。
そこで、気をよくしたA君に、今度は学校準拠の国語の問題集を初めからするようにと手渡すと、喜んで国語をするようになりました。すると1カ月ほどで、問題集の半分を終えてしまいました。
そして、いよいよ本題の算数の文章題に取り組むように勧めると、かつて、字も汚かったA君が、すごくきれいな字で、文章題の絵や図を書いて、問題を解きだしたのです。これには、本当に驚きました。
そして、どんどん、算数の文章題を解きだすのです。そして。嬉しそうに「先生、これ、おもしろいわ」と言うのです。今度は、算数の文章題に夢中になり、一心不乱に勉強しています。今では90分を集中して、考え続けるA君に変身してしまいました。
私たちがA君に教えてもらったこと。それは、無理やりさせる勉強より、達成感や、喜びを持ちながら、「考えるって楽しい。」という気持ちで勉強に向かうと、本当に可能性が開かれてゆくということでした。
A君にとっては、外遊びも、パズルも、国語の読解問題も、算数の文章題も「外遊び」の延長線上に位置しているのかも知れません。創意工夫しながら夢中で遊ぶ子が、創意工夫して「深く考える」勉強につながるよう、子ども達を応援したいと思いました。