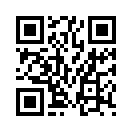2008年11月23日
お子さんが元気にイキイキになる接し方6
●靴をそろえることを家庭のルールにしましょう。
靴をそろえられる子は、成績が伸びてゆく生徒になります。勉強ができる生徒は、靴をそろえることや、椅子をなおすことができます。まずは親が守ってゆきます。そして、子どもとルールを決めましょう。小学生のうちであれば、習慣化することができると思います。しばらくは親が整理する時期もあっていいと思います。心の中で愚痴や文句を言いながら靴を整理するのではなく、この場を浄化させていただこうという思いで行為を行ないましょう。常に整理された状態を保ち続けることが、目に見えない風土になって、整理されていないことに違和感を子ども達にようになります。半年、1年かかってもいいと思います。こうした取り組みが、忘れ物やケアレスミスをなくすことにつながってゆきます。靴をそろえることと成績の相関関係は、学校の先生ならば、ほとんどの先生がご存知だと思います。そして、子どもがしないからといって、叱るのではなく、声掛けを続けましょう。生活習慣を変えることが、けじめをつけ、実は勉強にも大きく左右しているのです。さらに、将来、一つの仕事を任されたときにも、最後までやり通せたり、困難に出くわした時にもやりぬく力となってゆきます。
靴をそろえられる子は、成績が伸びてゆく生徒になります。勉強ができる生徒は、靴をそろえることや、椅子をなおすことができます。まずは親が守ってゆきます。そして、子どもとルールを決めましょう。小学生のうちであれば、習慣化することができると思います。しばらくは親が整理する時期もあっていいと思います。心の中で愚痴や文句を言いながら靴を整理するのではなく、この場を浄化させていただこうという思いで行為を行ないましょう。常に整理された状態を保ち続けることが、目に見えない風土になって、整理されていないことに違和感を子ども達にようになります。半年、1年かかってもいいと思います。こうした取り組みが、忘れ物やケアレスミスをなくすことにつながってゆきます。靴をそろえることと成績の相関関係は、学校の先生ならば、ほとんどの先生がご存知だと思います。そして、子どもがしないからといって、叱るのではなく、声掛けを続けましょう。生活習慣を変えることが、けじめをつけ、実は勉強にも大きく左右しているのです。さらに、将来、一つの仕事を任されたときにも、最後までやり通せたり、困難に出くわした時にもやりぬく力となってゆきます。
2008年11月08日
お子さんが元気にイキイキになる接し方5
お子さんが元気にイキイキになる接し方5
魔法のアクションクリプト
●将来の夢を語り合える親子関係をつくりましょう
子どもが家で勉強をしないことを、人のせいにしたり、もっと強制的に勉強をするように言って欲しいと言われる保護者の方もおられます。しかし、子どもが勉強しない環境を作ったのは、ご家庭なのです。一番の原因が家庭であるならば、その原因を取り除けば、子どもは勉強をするようになります。
例えば、点数ばかりに目がいって、結果を出さなければ子どもを叱るのは、大きな間違いです。考えることの楽しさや、自分で発見することの喜びや、結果よりも過程を大切にする関わりをされていたら、子どもたちは結果よりも、考えること、意味を知ること、発見すること、過程を知ることに重心が移ってゆきます。そんな子ども達は、勉強する時間や、考える時間、読書をする時間を楽しみとなり、それは自ずと、結果に現れてきます。さらに、中学生にもなると、子どもたちは意思が芽生えてきます。その意思を尊重し、将来の夢を語り合える親子関係ならば、子どもは、将来の夢と勉強がつながってゆき、勉強する必然を感じるのではないでしょうか。
そのような、関わりをぜひ、保護者の皆様、子ども達と作ってください。そして、行きたい高校を見つけ、その学校に足を運び、リアリティを持たせましょう。同時に、模擬テストを積極的に受験し、自分の今の学力でいけるかどうかを把握させましょう。現実を直視し、目標を持つ。こうした動機付けは、まさにお母さん方がその気になれば、いつからでもできることなのではないかと思います。
魔法のアクションクリプト
●将来の夢を語り合える親子関係をつくりましょう
子どもが家で勉強をしないことを、人のせいにしたり、もっと強制的に勉強をするように言って欲しいと言われる保護者の方もおられます。しかし、子どもが勉強しない環境を作ったのは、ご家庭なのです。一番の原因が家庭であるならば、その原因を取り除けば、子どもは勉強をするようになります。
例えば、点数ばかりに目がいって、結果を出さなければ子どもを叱るのは、大きな間違いです。考えることの楽しさや、自分で発見することの喜びや、結果よりも過程を大切にする関わりをされていたら、子どもたちは結果よりも、考えること、意味を知ること、発見すること、過程を知ることに重心が移ってゆきます。そんな子ども達は、勉強する時間や、考える時間、読書をする時間を楽しみとなり、それは自ずと、結果に現れてきます。さらに、中学生にもなると、子どもたちは意思が芽生えてきます。その意思を尊重し、将来の夢を語り合える親子関係ならば、子どもは、将来の夢と勉強がつながってゆき、勉強する必然を感じるのではないでしょうか。
そのような、関わりをぜひ、保護者の皆様、子ども達と作ってください。そして、行きたい高校を見つけ、その学校に足を運び、リアリティを持たせましょう。同時に、模擬テストを積極的に受験し、自分の今の学力でいけるかどうかを把握させましょう。現実を直視し、目標を持つ。こうした動機付けは、まさにお母さん方がその気になれば、いつからでもできることなのではないかと思います。
2008年11月03日
お子さんが元気にイキイキになる接し方4
お子さんが元気にイキイキになる接し方4
魔法のアクションクリプト
●本の読み聞かせは、小3までは続けましょう。
本の読み聞かせは、小3までは続けましょう。絵本の読み聞かせを、小学校で字を覚えたときからしなくなるお母さん方も多いのですが、これは、とてももったいないことです。子どもは字を読めるようになったとしても、言葉の意味やイメージを持つことがまだ十分ではありません。言葉は、読み手の持つイメージが、子ども達に広がってゆくからです。ですから、お母さんの読み聞かせこそ、子ども達の想像力、思考力を引き出し、心を豊かにすることのできる大切な時となるからです。
●一生懸命努力しているところを見つけてあげてください。そしてそれを誉めてあげましょう
私達は、どうしても子どもを見下げて、ああしなさい、こうしなさいと指示し、早くさせよう急がせてしまいがちです。そうなると子どもは、だんだん「指示待ち人間」となり、依存的になってゆきます。自分で考えようとしないために、ますます言われないとしない子どもになってゆきます。そういう姿を見て、さらに威圧的に関わったり、子どもを責めたりし、悪循環に陥るご家庭は多いのではないでしょうか。しかし、子どもたちは、本当は私達や親に応えようと懸命です。その姿を見つけようとすることがどれほど大切なことでしょうか。けなげに一生懸命努力しているところを見つけてあげてください。そしてそれを誉めてあげましょう。子どもが本当にしたいことを大切にしてあげていただきたいのです。
魔法のアクションクリプト
●本の読み聞かせは、小3までは続けましょう。
本の読み聞かせは、小3までは続けましょう。絵本の読み聞かせを、小学校で字を覚えたときからしなくなるお母さん方も多いのですが、これは、とてももったいないことです。子どもは字を読めるようになったとしても、言葉の意味やイメージを持つことがまだ十分ではありません。言葉は、読み手の持つイメージが、子ども達に広がってゆくからです。ですから、お母さんの読み聞かせこそ、子ども達の想像力、思考力を引き出し、心を豊かにすることのできる大切な時となるからです。
●一生懸命努力しているところを見つけてあげてください。そしてそれを誉めてあげましょう
私達は、どうしても子どもを見下げて、ああしなさい、こうしなさいと指示し、早くさせよう急がせてしまいがちです。そうなると子どもは、だんだん「指示待ち人間」となり、依存的になってゆきます。自分で考えようとしないために、ますます言われないとしない子どもになってゆきます。そういう姿を見て、さらに威圧的に関わったり、子どもを責めたりし、悪循環に陥るご家庭は多いのではないでしょうか。しかし、子どもたちは、本当は私達や親に応えようと懸命です。その姿を見つけようとすることがどれほど大切なことでしょうか。けなげに一生懸命努力しているところを見つけてあげてください。そしてそれを誉めてあげましょう。子どもが本当にしたいことを大切にしてあげていただきたいのです。
2008年10月31日
お子さんが元気にイキイキになる接し方3
お子さんが元気にイキイキになる接し方3
魔法のアクションクリプト
●同じ高さの目線で話をしましょう
お子さんと同じ高さの目線で話をしましょう。そうすることで、子どもたちは、心を開いてくれます。上からの目線では、威圧的になってしまい、子どもは心を閉ざしてしまいます。私たちも、塾で子ども達を一人一人見て回りながら、わからないところを説明する時、目の高さをあわせて質問したり教えたりします。なかなかそうできないことも多いのですが、これを意識することが、なかなか難しいことであることがわかります。お母さんも、お子さんの目線になって話をすることに、挑戦してみてください。そして、子どもの心の声を聞くようにしましょう。今までに聞こえなかったものが聞こえるかもしれません。
●子どもは、いつも何でも学びたがっています
「子どもは、いつも学びたがっている。」ということを心に置いていただきたいと思います。机の上でドリルや問題集をしている時だけが勉強のように錯覚される方も多くおられますが、テレビや家族の会話や、町を歩いている時でも、子どもたちは、「これってどういうこと?」「なぜそんな風にするの?」と聞いてくる場合があります。そんな時、子どもの目の前に映像が出てくるように、説明してあげることが保護者の方の役割です。その機会が増えれば増えるほど、子ども達の可能性は広がってゆきます。
●勉強した後は、必ず机の上には何も置いていない状態になるよう、習慣づけてあげましょう
勉強した後は、必ず机の上には何も置いていない状態になるよう、習慣づけてあげましょう。何もなくて気持ちのいい感覚を味わわせてあげることが大切です。そして、物事には必ず起承転結があり、スッキリと終わった状態になるように、習慣づくまでは、横でお母さんがついてあげていただければと思います。そして、片付けた後は、ぜひ褒めていただきたいと思います。
魔法のアクションクリプト
●同じ高さの目線で話をしましょう
お子さんと同じ高さの目線で話をしましょう。そうすることで、子どもたちは、心を開いてくれます。上からの目線では、威圧的になってしまい、子どもは心を閉ざしてしまいます。私たちも、塾で子ども達を一人一人見て回りながら、わからないところを説明する時、目の高さをあわせて質問したり教えたりします。なかなかそうできないことも多いのですが、これを意識することが、なかなか難しいことであることがわかります。お母さんも、お子さんの目線になって話をすることに、挑戦してみてください。そして、子どもの心の声を聞くようにしましょう。今までに聞こえなかったものが聞こえるかもしれません。
●子どもは、いつも何でも学びたがっています
「子どもは、いつも学びたがっている。」ということを心に置いていただきたいと思います。机の上でドリルや問題集をしている時だけが勉強のように錯覚される方も多くおられますが、テレビや家族の会話や、町を歩いている時でも、子どもたちは、「これってどういうこと?」「なぜそんな風にするの?」と聞いてくる場合があります。そんな時、子どもの目の前に映像が出てくるように、説明してあげることが保護者の方の役割です。その機会が増えれば増えるほど、子ども達の可能性は広がってゆきます。
●勉強した後は、必ず机の上には何も置いていない状態になるよう、習慣づけてあげましょう
勉強した後は、必ず机の上には何も置いていない状態になるよう、習慣づけてあげましょう。何もなくて気持ちのいい感覚を味わわせてあげることが大切です。そして、物事には必ず起承転結があり、スッキリと終わった状態になるように、習慣づくまでは、横でお母さんがついてあげていただければと思います。そして、片付けた後は、ぜひ褒めていただきたいと思います。