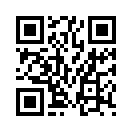2009年10月25日
「イデア進学ゼミ」が提案する、小学生のための勉強ガイド4
5.丸つけの仕方で勉強の意欲が変わる!
丸つけはとても重要です。低学年でしたら親が丸つけをする場合、太い赤ペンで大きくつけてあげましょう。
がんばった時は花マルや漫画を添えてあげるのもいいと思います。
また、計算問題などでは、間違いを大きなバツで書かない方が良いでしょう。バツは小さなチェックか、子どもによっては丸をつけないでそのままにしてあげるのもいいと思います。子どもたちは、間違うことをとても悪いことのように錯覚しています。
今の学校の先生方も、ご両親の世代も、子どもたちの間違った問題を見ると「なぜこんなやり方をしたんだ。わかってないなあ。教えてやらないと」という気持ちに駆り立てられる方が多いのではないでしょうか。特にわが子に対しては、なかなか冷静になれず、感情的になりやすいものです。ですから、バツになると子どもたちにとっては、親に怒られる、責められると思ってしまうのではないでしょうか。
2回目にやり直して丸になった時は、朱色やオレンジ色などを使うと良いでしょう。そして丸つけをするときは、必ず声をかけ、「すごいね。よくできたね。」など、一緒に喜びましょう。喜びのエネルギーを回してゆくこと。これがこどもたちの意欲を引き出します。
丸つけはとても重要です。低学年でしたら親が丸つけをする場合、太い赤ペンで大きくつけてあげましょう。
がんばった時は花マルや漫画を添えてあげるのもいいと思います。
また、計算問題などでは、間違いを大きなバツで書かない方が良いでしょう。バツは小さなチェックか、子どもによっては丸をつけないでそのままにしてあげるのもいいと思います。子どもたちは、間違うことをとても悪いことのように錯覚しています。
今の学校の先生方も、ご両親の世代も、子どもたちの間違った問題を見ると「なぜこんなやり方をしたんだ。わかってないなあ。教えてやらないと」という気持ちに駆り立てられる方が多いのではないでしょうか。特にわが子に対しては、なかなか冷静になれず、感情的になりやすいものです。ですから、バツになると子どもたちにとっては、親に怒られる、責められると思ってしまうのではないでしょうか。
2回目にやり直して丸になった時は、朱色やオレンジ色などを使うと良いでしょう。そして丸つけをするときは、必ず声をかけ、「すごいね。よくできたね。」など、一緒に喜びましょう。喜びのエネルギーを回してゆくこと。これがこどもたちの意欲を引き出します。
2009年10月17日
「イデア進学ゼミ」が提案する、小学生のための勉強ガイド3
3.「目的を達成するために工夫する力」=「人間力」を養いましょう
「目的を達成するために工夫する力」…これは、私の塾でも、とても大切にしているキーワードです。目的を達成するためには、どうしても、自分が大切にしているものを一つに絞ってゆく必要があります。自分がやりたいことを我慢し、その時間を集中して目的達成のために努力しなければならないからです。こんな時に、忍耐力がつきます。そして、テストの点数では反映されない「人間力」がついてゆくのです。この人間力は、将来とても大きな力になります。
私たちの塾で、文章題を中心にしているのは、こうした「人間力」を養うためにあると言っても過言ではありません。一つの問題を徹底的に考え抜く力、忍耐力、目的を達成した時の喜びを味わうこと・・・こうした力が育まれています。ご家庭でできることとして、文章題でも、パズルでも構いませんので、ぜひ、週に1度でもこうした時間を作って差し上げてください。
4.5年生までと6年生とでは、勉強の仕方を分けて考えます
5年生までのお子さんは、徹底した思考力の養成が必要と思います。思考力を身につけるのは、小学5年生までが最適です。頭が柔らかいこの時期にしかできないことをしてあげるべきだと思います。
しかし、6年生は違います。間もなく中学に入るわけですし、このくらいのお子さんは、暗記力が優れています。鍛えればどんどん覚えることができます。そのためには英語の暗記は最も適しています。暗記力がつくと、他の科目もなんでも暗記できるようになってしまうのが驚きです。また、英語や算数計算を通して、きれいな字で正しいノートの書き方を覚えてゆきましょう。
また、6年生には、ぜひ、中学校での勉強の仕方、授業の聞き方、テストの受け方、心構えなどを、説明してあげましょう。そして、ぜひ歴史に興味を向けてもらいたいと思います。歴史に出てくる人物の伝記や漫画でも構いません。どんどん本を読ませましょう。必ずお子さんの人生に大きな良い影響を与えることでしょう。歴史の大きな図鑑なども、買ってあげるのもいいかもしれません。歴史の漫画も大賛成です。
さらに、理科の漫画など買いそろえてあげるといいと思います。学研の「科学と学習」なんかもお子さんが興味を持てば、買ってあげてほしいものです。
お子さんには、無限の可能性があります。とにかく基本は、お子さんがやりたいと思ってやるように、ご両親ができるのは、環境を整えることと「なぜ、こう思うのだろう、なぜこうなったと思う?など、「問いかけ」をして上げることだと思います。
「目的を達成するために工夫する力」…これは、私の塾でも、とても大切にしているキーワードです。目的を達成するためには、どうしても、自分が大切にしているものを一つに絞ってゆく必要があります。自分がやりたいことを我慢し、その時間を集中して目的達成のために努力しなければならないからです。こんな時に、忍耐力がつきます。そして、テストの点数では反映されない「人間力」がついてゆくのです。この人間力は、将来とても大きな力になります。
私たちの塾で、文章題を中心にしているのは、こうした「人間力」を養うためにあると言っても過言ではありません。一つの問題を徹底的に考え抜く力、忍耐力、目的を達成した時の喜びを味わうこと・・・こうした力が育まれています。ご家庭でできることとして、文章題でも、パズルでも構いませんので、ぜひ、週に1度でもこうした時間を作って差し上げてください。
4.5年生までと6年生とでは、勉強の仕方を分けて考えます
5年生までのお子さんは、徹底した思考力の養成が必要と思います。思考力を身につけるのは、小学5年生までが最適です。頭が柔らかいこの時期にしかできないことをしてあげるべきだと思います。
しかし、6年生は違います。間もなく中学に入るわけですし、このくらいのお子さんは、暗記力が優れています。鍛えればどんどん覚えることができます。そのためには英語の暗記は最も適しています。暗記力がつくと、他の科目もなんでも暗記できるようになってしまうのが驚きです。また、英語や算数計算を通して、きれいな字で正しいノートの書き方を覚えてゆきましょう。
また、6年生には、ぜひ、中学校での勉強の仕方、授業の聞き方、テストの受け方、心構えなどを、説明してあげましょう。そして、ぜひ歴史に興味を向けてもらいたいと思います。歴史に出てくる人物の伝記や漫画でも構いません。どんどん本を読ませましょう。必ずお子さんの人生に大きな良い影響を与えることでしょう。歴史の大きな図鑑なども、買ってあげるのもいいかもしれません。歴史の漫画も大賛成です。
さらに、理科の漫画など買いそろえてあげるといいと思います。学研の「科学と学習」なんかもお子さんが興味を持てば、買ってあげてほしいものです。
お子さんには、無限の可能性があります。とにかく基本は、お子さんがやりたいと思ってやるように、ご両親ができるのは、環境を整えることと「なぜ、こう思うのだろう、なぜこうなったと思う?など、「問いかけ」をして上げることだと思います。
2009年10月13日
「イデア進学ゼミ」が提案する、小学生のための勉強ガイド2
2.勉強が出来る三つの習慣
勉強ができる子には3つの特徴と習慣があると言われています。それは、
?返事ができる。?あいさつができる。?椅子・靴を揃えられる
というものです。
私はこの話を聞いた時、確かに当たっていると感心しました。
さらに付け加えると、「頭の良い子」がこの三つの習慣を兼ね備えているとは限らないことも実感しています。小学校で頭の良い生徒であっても、上記の習慣を持っていない生徒は、中学校で伸び悩んでしまいます。
頭の良い子、良く考える子に育てることに加えて、上記のような、日々の行いに責任の持てるように育むことがとても大切なことだと思います。そして、勉強ができるようになるためだけに、このことを実践するというのではなく、学習意欲があり、集中力があり、責任感も強い子どもになってもらうために、取り組んでもらえたらと思います。
当然、子どもの幼いころからの家庭環境や気質の問題から、上記の三つの習慣を持ちにくい子どもたちがたくさんいると思います。だからこそ、保護者ができることがあります。子どもたちは、保護者の方を見て行動しているからです。
勉強ができる子には3つの特徴と習慣があると言われています。それは、
?返事ができる。?あいさつができる。?椅子・靴を揃えられる
というものです。
私はこの話を聞いた時、確かに当たっていると感心しました。
さらに付け加えると、「頭の良い子」がこの三つの習慣を兼ね備えているとは限らないことも実感しています。小学校で頭の良い生徒であっても、上記の習慣を持っていない生徒は、中学校で伸び悩んでしまいます。
頭の良い子、良く考える子に育てることに加えて、上記のような、日々の行いに責任の持てるように育むことがとても大切なことだと思います。そして、勉強ができるようになるためだけに、このことを実践するというのではなく、学習意欲があり、集中力があり、責任感も強い子どもになってもらうために、取り組んでもらえたらと思います。
当然、子どもの幼いころからの家庭環境や気質の問題から、上記の三つの習慣を持ちにくい子どもたちがたくさんいると思います。だからこそ、保護者ができることがあります。子どもたちは、保護者の方を見て行動しているからです。
2009年10月09日
「イデア進学ゼミ」が提案する、小学生のための勉強ガイド1
1、規則正しい生活と朝型の勉強習慣をつけましょう
私は、ぜひ、子どもたちに正しい生活習慣をつけることをお勧めしたいと思います。最近の子どもたちは夜型の生活になりやすく、夜食を摂って、テレビやゲームをして夜遅くまで起きていると子どもたちも少なくありません。文部科学省が2006 年に中学生に休日の過ごし方を尋ねたところ、第一位はなんと、睡眠不足の解消という結果になっています。
さらに大きな問題が生活の夜型化。同じ文部科学省の調査結果では、深夜24 時以降に眠る小学4 年生が5.1%、5 年生で7.6%、6 年生で11.8%。中学1年生で35.2%、2 年生で52.5%、3 年生で64.4%となっていて、睡眠不足だけでなく、子どもの生活が完全に夜型化している実態が浮き彫りになっています。逆に、全国学力検査で毎年トップになる秋田県は「早寝・早起き・朝ご飯」という子どもたちの生活習慣が大きな要因になっていると言われています。
ご家庭それぞれに状況が違うでしょうが、たとえば、保護者の方が今までより少し早起きしてお子さんとランニングをするというはどうでしょうか。朝6時に起きて、少し近所を一緒に走ってみる。そのあとで、朝食まで、あるいは学校に行くまで、少し勉強するなんていいかもしれません。勉強する内容は、どんなものでもいいでしょう。計算問題でも漢字でも、本読みでも、パズルでも、文章問題1問でもいいのです。親がいくつかコースを作って、そこから選ばせてあげるのもいいと思います。
ここで大切なポイントは、「親は教えこまない」ということです。あくまでも、その子が、ストレスを感じないで、夢中になるように自分で気づけるように、環境を作って差し上げることではないかと思います。
親子でランニングをするとき、(散歩でもいいかもしれません。一緒に犬の散歩をするのでもいいでしょう。)お勧めしたいのは、お子さんの学校でのことや、昨日あったこと、いやだったこと、楽しかったこと、うれしかったこと、などじっくり聞いて差し上げてほしいのです。すると、普段聞けないことをお子さんから聞けるかもしれません。実はこんなことで困っているとか、最近算数がわからなくなってきたとか、友達と喧嘩をしてしまって気まずくなっているとか、まずその子のすべてを受けとめてあげるというのはどうでしょうか。答えは出せなくてもいいのです。大切なのは、一緒に苦しみ、一緒に喜ぶところではないかなと思います。
私は、ぜひ、子どもたちに正しい生活習慣をつけることをお勧めしたいと思います。最近の子どもたちは夜型の生活になりやすく、夜食を摂って、テレビやゲームをして夜遅くまで起きていると子どもたちも少なくありません。文部科学省が2006 年に中学生に休日の過ごし方を尋ねたところ、第一位はなんと、睡眠不足の解消という結果になっています。
さらに大きな問題が生活の夜型化。同じ文部科学省の調査結果では、深夜24 時以降に眠る小学4 年生が5.1%、5 年生で7.6%、6 年生で11.8%。中学1年生で35.2%、2 年生で52.5%、3 年生で64.4%となっていて、睡眠不足だけでなく、子どもの生活が完全に夜型化している実態が浮き彫りになっています。逆に、全国学力検査で毎年トップになる秋田県は「早寝・早起き・朝ご飯」という子どもたちの生活習慣が大きな要因になっていると言われています。
ご家庭それぞれに状況が違うでしょうが、たとえば、保護者の方が今までより少し早起きしてお子さんとランニングをするというはどうでしょうか。朝6時に起きて、少し近所を一緒に走ってみる。そのあとで、朝食まで、あるいは学校に行くまで、少し勉強するなんていいかもしれません。勉強する内容は、どんなものでもいいでしょう。計算問題でも漢字でも、本読みでも、パズルでも、文章問題1問でもいいのです。親がいくつかコースを作って、そこから選ばせてあげるのもいいと思います。
ここで大切なポイントは、「親は教えこまない」ということです。あくまでも、その子が、ストレスを感じないで、夢中になるように自分で気づけるように、環境を作って差し上げることではないかと思います。
親子でランニングをするとき、(散歩でもいいかもしれません。一緒に犬の散歩をするのでもいいでしょう。)お勧めしたいのは、お子さんの学校でのことや、昨日あったこと、いやだったこと、楽しかったこと、うれしかったこと、などじっくり聞いて差し上げてほしいのです。すると、普段聞けないことをお子さんから聞けるかもしれません。実はこんなことで困っているとか、最近算数がわからなくなってきたとか、友達と喧嘩をしてしまって気まずくなっているとか、まずその子のすべてを受けとめてあげるというのはどうでしょうか。答えは出せなくてもいいのです。大切なのは、一緒に苦しみ、一緒に喜ぶところではないかなと思います。
2009年09月14日
低学年のお子さんで基礎的な計算がお困りの保護者の方へ
●低学年のお子さんで基礎的な計算がお困りの保護者の方へ
小学校低学年で計算が遅いとか、学校の宿題が遅い、計算問題を嫌がるなどで、お困りの方は、小学館の「プレ百ます計算」はお勧めです。この本は、計算するときに、楽に繰り上がりの足し算や引き算ができるやり方をマスターさせてくれます。
小学校低学年で計算が遅いとか、学校の宿題が遅い、計算問題を嫌がるなどで、お困りの方は、小学館の「プレ百ます計算」はお勧めです。この本は、計算するときに、楽に繰り上がりの足し算や引き算ができるやり方をマスターさせてくれます。
2009年09月08日
小学生で漢字の習得でお困りの保護者の方へ
小学生で漢字の習得でお困りの保護者の方へ
漢字をなかなかな覚えない、筆順がムチャクチャ、じを丁寧に書けない、等でお困りの方は、同じく小学館の「徹底反復 書き順プリント」がよいと思います。
ただし、使い方にひと工夫必要です。漢字は、何度も同じ漢字を書かさない方がベストです。なぜなら何度も同じ漢字を書くのは子どもが嫌がるようになるからです。すでに、漢字を嫌がっているのは、同じ漢字を何度も書かされているからでしょう。
それよりも、一つの漢字を1文字か2文字練習させるのです。もちろん、筆順だけはチェックしてあげてください。そして、「2文字までしか書いては駄目よ」と言っておきます。このテキストには、7文字練習できるようになっていますが、そのうち、2文字は、上からなぞるようになっています。このなぞるところは、使わない方がよいでしょう。なぞるのではなく、文字を見て写す方が力はつきます。このテキストのよいところは、すぐ横にお手本が何回も書かれてあるので、子どもがお手本をじっくり見るように工夫されています。
さらに、見開き2ページの中で子どもが書きたい漢字を選ばせると良いかと思います。「一番練習したい漢字はどれ?」と聞いてあげてください。喜んで選ぶと思います。2ページから一文字を選んで、1回か2回練習する。その繰り返しを、6文字から10文字するのはどうでしょうか。毎日ほんの5分か10分で、みるみる漢字が好きになり、得意になってゆくと思います。
それと、この本には、学年ごとの全漢字音読というページもあります。毎日これを声を出して読ませると良いと思います。読みに強くなることは、読解力の向上につながります。お母さんは、その時に、言葉の意味も説明してあげてください。言えなかった漢字には○をつけて、また次の日は、言えなかったところだけを読ませてみてください。言えたら○を消してあげると、達成感が味わえるのではないでしょうか。
漢字をなかなかな覚えない、筆順がムチャクチャ、じを丁寧に書けない、等でお困りの方は、同じく小学館の「徹底反復 書き順プリント」がよいと思います。
ただし、使い方にひと工夫必要です。漢字は、何度も同じ漢字を書かさない方がベストです。なぜなら何度も同じ漢字を書くのは子どもが嫌がるようになるからです。すでに、漢字を嫌がっているのは、同じ漢字を何度も書かされているからでしょう。
それよりも、一つの漢字を1文字か2文字練習させるのです。もちろん、筆順だけはチェックしてあげてください。そして、「2文字までしか書いては駄目よ」と言っておきます。このテキストには、7文字練習できるようになっていますが、そのうち、2文字は、上からなぞるようになっています。このなぞるところは、使わない方がよいでしょう。なぞるのではなく、文字を見て写す方が力はつきます。このテキストのよいところは、すぐ横にお手本が何回も書かれてあるので、子どもがお手本をじっくり見るように工夫されています。
さらに、見開き2ページの中で子どもが書きたい漢字を選ばせると良いかと思います。「一番練習したい漢字はどれ?」と聞いてあげてください。喜んで選ぶと思います。2ページから一文字を選んで、1回か2回練習する。その繰り返しを、6文字から10文字するのはどうでしょうか。毎日ほんの5分か10分で、みるみる漢字が好きになり、得意になってゆくと思います。
それと、この本には、学年ごとの全漢字音読というページもあります。毎日これを声を出して読ませると良いと思います。読みに強くなることは、読解力の向上につながります。お母さんは、その時に、言葉の意味も説明してあげてください。言えなかった漢字には○をつけて、また次の日は、言えなかったところだけを読ませてみてください。言えたら○を消してあげると、達成感が味わえるのではないでしょうか。
2009年08月21日
勉強を楽しむ
勉強を楽しむ
子どもたちの生きる力を考えるとき、子どもたちが、心から楽しんでそれをしているかどうかが、大きなポイントであるように思います。
たとえば、小学生が、塾の文章題をあれこれ考えながら、生き生きと楽しんでいる姿、中学生が、中間期末テスト前や、入試前に、充実しながら勉強に取り組んでいる姿などを見るたびに、一番伸びているのはこの時期だと思えてなりません。それも、難問に挑戦しているときほど、この効果は高いと思います。
自分の力より、少しだけ高い問題を与え続け、生き生きと取り組む子どもたちの状況を常に作りだすことが、塾のすべきことなのではないかと思っています。
子どもたちの生きる力を考えるとき、子どもたちが、心から楽しんでそれをしているかどうかが、大きなポイントであるように思います。
たとえば、小学生が、塾の文章題をあれこれ考えながら、生き生きと楽しんでいる姿、中学生が、中間期末テスト前や、入試前に、充実しながら勉強に取り組んでいる姿などを見るたびに、一番伸びているのはこの時期だと思えてなりません。それも、難問に挑戦しているときほど、この効果は高いと思います。
自分の力より、少しだけ高い問題を与え続け、生き生きと取り組む子どもたちの状況を常に作りだすことが、塾のすべきことなのではないかと思っています。
2009年08月14日
子どもたちの人間力とは
子どもたちの人間力とは
子どもたちが、苦手なこと、いやなことを目の前にしたときに、「逃げたり、投げ出したり、あきらめたり」しないようになるならば、これは子どもたちの人間的成長とは言えないでしょうか。子どもたちがこうしたことが、できるようになるには、どうすればよいのでしょうか。
まず、第一に、自分自身を知るということから始まるように思います。自分の性格が、短気なのか、のんびり屋なのか、やりたいようにやりたいと思うタイプなのか、すぐに駄目だと自己否定してしまうのか。こうした、自分の性格や、よく出てくる思い癖などが、くっきりと見つけることができれば、子どもたちは、自分のこの気持ちが、この結果をうんでしまったんだと思えることでしょう。こうした、「自己発見」や、「自己受納」は、非常に大切な要因となると思います。
こうした自分自身の姿をあるがまま受けとめられるようになれば、どれほど力強いでしょうか。自らの弱点を克服できる力強い子どもの育みに、私たちは挑戦しています。
子どもたちが、苦手なこと、いやなことを目の前にしたときに、「逃げたり、投げ出したり、あきらめたり」しないようになるならば、これは子どもたちの人間的成長とは言えないでしょうか。子どもたちがこうしたことが、できるようになるには、どうすればよいのでしょうか。
まず、第一に、自分自身を知るということから始まるように思います。自分の性格が、短気なのか、のんびり屋なのか、やりたいようにやりたいと思うタイプなのか、すぐに駄目だと自己否定してしまうのか。こうした、自分の性格や、よく出てくる思い癖などが、くっきりと見つけることができれば、子どもたちは、自分のこの気持ちが、この結果をうんでしまったんだと思えることでしょう。こうした、「自己発見」や、「自己受納」は、非常に大切な要因となると思います。
こうした自分自身の姿をあるがまま受けとめられるようになれば、どれほど力強いでしょうか。自らの弱点を克服できる力強い子どもの育みに、私たちは挑戦しています。
2009年08月07日
教師の質を向上する
教師の質を向上する
私どもの塾は、塾長と副塾長の二人だけで行っています。私たちは、子どもたちの学力の向上、人間性の向上を第一目的に考えるならば、どうしても教師の質の向上が必要不可欠と考えています。
なぜならば、教師と子どもたちは響きあい、成長しあう存在であるからです。それはあたかも写し鏡のように、響き合っているように思えます。だとするならば、教師の側が、常に向上し続ける必要があるでしょう。
たとえば、講師間で人間関係がうまくいっていなければ、それは子どもたちやクラスの雰囲気に確実に伝わってゆくでしょう。教師の数が少なくても、本当に協力しあう関係であるならば、それは、必ず子どもたちに良い影響を与えると考えます。そのことが私どもが、アルバイトの講師を入れていない理由です。アルバイトの講師が悪いということではありませんが、講師の育成には本当に大変な時間と労力が必要となります。そのため、私どもは、そこにエネルギーを使うものを、子どもたちの成長のために使いたいと考えています。
どれだけ、子どもたち一人ひとりのことを考え、子どもたちの良きアドバイザーとなりうるか、そのために、講師の質を高める努力は本当に大切です。まだまだ足りないところはありますが、努力し、向上し続けてゆきたいと思います。
私どもの塾は、塾長と副塾長の二人だけで行っています。私たちは、子どもたちの学力の向上、人間性の向上を第一目的に考えるならば、どうしても教師の質の向上が必要不可欠と考えています。
なぜならば、教師と子どもたちは響きあい、成長しあう存在であるからです。それはあたかも写し鏡のように、響き合っているように思えます。だとするならば、教師の側が、常に向上し続ける必要があるでしょう。
たとえば、講師間で人間関係がうまくいっていなければ、それは子どもたちやクラスの雰囲気に確実に伝わってゆくでしょう。教師の数が少なくても、本当に協力しあう関係であるならば、それは、必ず子どもたちに良い影響を与えると考えます。そのことが私どもが、アルバイトの講師を入れていない理由です。アルバイトの講師が悪いということではありませんが、講師の育成には本当に大変な時間と労力が必要となります。そのため、私どもは、そこにエネルギーを使うものを、子どもたちの成長のために使いたいと考えています。
どれだけ、子どもたち一人ひとりのことを考え、子どもたちの良きアドバイザーとなりうるか、そのために、講師の質を高める努力は本当に大切です。まだまだ足りないところはありますが、努力し、向上し続けてゆきたいと思います。
2009年08月01日
義務感から自発的な意志へ
義務感から自発的な意志へ
塾では、宿題を毎回出していますが、この宿題を「義務感でいやいやする」ところから、「自発的に意思を持って行う」ところにスイッチできるかどうかが大切なポイントだと感じています。
中学3年生にもなると、出された宿題だけをしているくらいでは、とても志望校に合格できるものではありません。目的を持つ。そしてそれに向かって、自分の意志で勉強をすることが重要です。最初は、習慣をつけるための宿題であっても、やりたくてする勉強へと変わる時、子どもたちの心は次の次元に成長したということではないかと思います。塾では、さまざま工夫を各学年で行い、子どもたちのやる気を応援しています。
塾では、宿題を毎回出していますが、この宿題を「義務感でいやいやする」ところから、「自発的に意思を持って行う」ところにスイッチできるかどうかが大切なポイントだと感じています。
中学3年生にもなると、出された宿題だけをしているくらいでは、とても志望校に合格できるものではありません。目的を持つ。そしてそれに向かって、自分の意志で勉強をすることが重要です。最初は、習慣をつけるための宿題であっても、やりたくてする勉強へと変わる時、子どもたちの心は次の次元に成長したということではないかと思います。塾では、さまざま工夫を各学年で行い、子どもたちのやる気を応援しています。