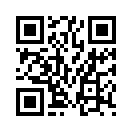2008年03月22日
生活習慣と勉強は、深くつながっている…。
生活習慣と勉強は、深くつながっている…。
ノートのとり方、ノートの使い方、字の書き方等で、学力のつき方がとても変わってきます。
塾では、ノートの取り方や使い方、ケアレスミスの少なくする数式の書き方など、折りあるごとにアドバイスしています。
以前、すぐに集中力が切れて私語をしてしまうお子さんがおられました。
よくノートを見ると字はていねいなのですが、とても小さな字を書くのです。
それで、私は「疲れない?」と聞くと「すぐに疲れちゃう」と答えてくれました。
私語をしてしまう謎がとけました。字が小さすぎて、疲れてしまい、見直しをしようとするとイライラしてしまうのでしょう。
私は、ゆっくりと、大きな字を書く意義を説明し、実験してもらいました。
案の定、この方が楽だとの返事をくれました。それ以降、とても大きな字で、ノートを広々と使うようになったのです。
集中力が途切れなくなり、私語がなくなったばかりでなく、成績が伸び、性格まで穏やかになってこられました。
生活習慣と勉強は、とても深くつながっていることを感じています。
ノートのとり方、ノートの使い方、字の書き方等で、学力のつき方がとても変わってきます。
塾では、ノートの取り方や使い方、ケアレスミスの少なくする数式の書き方など、折りあるごとにアドバイスしています。
以前、すぐに集中力が切れて私語をしてしまうお子さんがおられました。
よくノートを見ると字はていねいなのですが、とても小さな字を書くのです。
それで、私は「疲れない?」と聞くと「すぐに疲れちゃう」と答えてくれました。
私語をしてしまう謎がとけました。字が小さすぎて、疲れてしまい、見直しをしようとするとイライラしてしまうのでしょう。
私は、ゆっくりと、大きな字を書く意義を説明し、実験してもらいました。
案の定、この方が楽だとの返事をくれました。それ以降、とても大きな字で、ノートを広々と使うようになったのです。
集中力が途切れなくなり、私語がなくなったばかりでなく、成績が伸び、性格まで穏やかになってこられました。
生活習慣と勉強は、とても深くつながっていることを感じています。
2008年03月19日
感性と知性を育む教育が大切です
感性と知性を育む教育が、本当の基礎学力と実力をついてゆきます。
小学4〜5年生くらいから、塾に入った生徒が、どんどん賢くなってきています。私たちの塾は、一切詰め込みをしません。パターンも教えません。もちろん、中学生以上になると、そうではありませんが、小学校の間は、様々な勉強に興味を持ってもらい、考えることが大好きになってもらうことを目標にしています。ですから、私たちの塾の小学生の子どもたちは、しばらく続けていると
? 本を読むのが大好きになります。
? さらに、算数の難しい文章題を考えるのが大好きになります。
? 根気と集中力のある子に育ちます。
? 作文が得意になります。
? 国語の読解問題が得意になります。
? 学校の勉強らしいことをしないのに、学校のテストや通知表が上がります。
? 塾が大好きになります。
? 理科や歴史に興味のある子になります。(高学年)
? 歴史に登場する偉人の人生から、人間として憧れる生き方を学んでゆきます。
? 人と比較して気持ちが乱れることが少なくなり、自分としてやるべきことを精一杯しようと思うようになります。
? ケアレスミスが少なくなります。
? 礼儀正しくなります。
他にも、学校のクラスで一人しか解けないような問題を解く子や、人に説明するのがうまくなったという子、考え方が論理的になってきたり、発表に自信が持てなかった生徒が自信を持って手を挙げて発表するようになったりと、様々な生徒が生まれています。
保護者の方が、私たちの指導の仕方を「おもしろい。ぜひ習わせたい」と共感していただければいただくほどに、効果が高くなります。
ぜひ、塾説明会にお越しください。随時、予約受け付けています。
小学4〜5年生くらいから、塾に入った生徒が、どんどん賢くなってきています。私たちの塾は、一切詰め込みをしません。パターンも教えません。もちろん、中学生以上になると、そうではありませんが、小学校の間は、様々な勉強に興味を持ってもらい、考えることが大好きになってもらうことを目標にしています。ですから、私たちの塾の小学生の子どもたちは、しばらく続けていると
? 本を読むのが大好きになります。
? さらに、算数の難しい文章題を考えるのが大好きになります。
? 根気と集中力のある子に育ちます。
? 作文が得意になります。
? 国語の読解問題が得意になります。
? 学校の勉強らしいことをしないのに、学校のテストや通知表が上がります。
? 塾が大好きになります。
? 理科や歴史に興味のある子になります。(高学年)
? 歴史に登場する偉人の人生から、人間として憧れる生き方を学んでゆきます。
? 人と比較して気持ちが乱れることが少なくなり、自分としてやるべきことを精一杯しようと思うようになります。
? ケアレスミスが少なくなります。
? 礼儀正しくなります。
他にも、学校のクラスで一人しか解けないような問題を解く子や、人に説明するのがうまくなったという子、考え方が論理的になってきたり、発表に自信が持てなかった生徒が自信を持って手を挙げて発表するようになったりと、様々な生徒が生まれています。
保護者の方が、私たちの指導の仕方を「おもしろい。ぜひ習わせたい」と共感していただければいただくほどに、効果が高くなります。
ぜひ、塾説明会にお越しください。随時、予約受け付けています。
2008年02月29日
新小学1年生との出会い
新小学1年生との出会い
先日、塾生の保護者の方から、下の子が今度、小学1年になるのだけれど、塾に入れてもらえないかとのご相談がありました。
当塾は、小学2年生からなのですが、小学1年の終わりでも、集中力と根気があるお子さんの場合は、面接の上、入塾いただくケースがあります。昨年も1年生の終わりに、そうした生徒が二人来られて、入塾されました。その子達が、ものすごく喜んで塾に来られているということと、とても思考力や国語・算数の力が伸びているのを見ておられて、今回、お電話をいただくことになりました。
今度、新小学1年生なら、ひらがなも読み書きできるかどうかわからないし、どんなものだろうかと思いながら、とりあえずお子さんと一緒に来ていただいて面接させていただくことにしました。
新小学1年生になるその子に、当塾の算数の文章問題をしていただいたのですが、私自身が驚くことになりました。長い文章を、ほぼ正確に読み取って絵や図にしているのです。その絵がとてもユニークで、意味をつかんでいることがよくわかりました。ひらがなや数字は、最近練習しだしているところのようなので、正確に書けない字もあるのですが、文章を読み取る力は、相当なものだと思いました。そして、夢中になって解いているのです。これならば、入塾されても十分に伸びてゆくと判断し、来ていただくことにしました。
聞けば、本が大好きで、何でもとても興味があるとのこと。私は小学生の間は、「楽しんで勉強する」ことがとても大切だと感じています。小学校に入学するまでに、じっくり、ゆっくり、お絵かきを楽しんだり、本を読んだりしてゆくならば、このように書くことには慣れていなくても、「考える力」は育まれてゆくことを、実感しました。
先日、塾生の保護者の方から、下の子が今度、小学1年になるのだけれど、塾に入れてもらえないかとのご相談がありました。
当塾は、小学2年生からなのですが、小学1年の終わりでも、集中力と根気があるお子さんの場合は、面接の上、入塾いただくケースがあります。昨年も1年生の終わりに、そうした生徒が二人来られて、入塾されました。その子達が、ものすごく喜んで塾に来られているということと、とても思考力や国語・算数の力が伸びているのを見ておられて、今回、お電話をいただくことになりました。
今度、新小学1年生なら、ひらがなも読み書きできるかどうかわからないし、どんなものだろうかと思いながら、とりあえずお子さんと一緒に来ていただいて面接させていただくことにしました。
新小学1年生になるその子に、当塾の算数の文章問題をしていただいたのですが、私自身が驚くことになりました。長い文章を、ほぼ正確に読み取って絵や図にしているのです。その絵がとてもユニークで、意味をつかんでいることがよくわかりました。ひらがなや数字は、最近練習しだしているところのようなので、正確に書けない字もあるのですが、文章を読み取る力は、相当なものだと思いました。そして、夢中になって解いているのです。これならば、入塾されても十分に伸びてゆくと判断し、来ていただくことにしました。
聞けば、本が大好きで、何でもとても興味があるとのこと。私は小学生の間は、「楽しんで勉強する」ことがとても大切だと感じています。小学校に入学するまでに、じっくり、ゆっくり、お絵かきを楽しんだり、本を読んだりしてゆくならば、このように書くことには慣れていなくても、「考える力」は育まれてゆくことを、実感しました。
2008年02月20日
新小6生対象の理科・社会の授業
新小6生対象の理科・社会の授業
塾では、新小学6年生を対象にした理科や社会の講義を週に1度行なっています。
特にこの時期、歴史に興味を持たせてあげられるかが大きな分岐点になります。
塾で説明を受けると、歴史に興味が出て、調べたくなってくるようです。
特に、歴史上の出来事だけでなく、その出来事が起こる因果関係を、詳しく説明してあげると、とても関心を持ち出します。
興味さえ持てば、子どもたちは趣味のように歴史の本を読み出します。
さらに、覚え方など教えると、覚え方にも感動してくれます。
どんなことも素直に吸収していけるこの時期に興味を持たせ、歴史が大好きになるようになればなあと思います。
中学・高校になって、楽しみながら勉強し、歴史が得意科目になるように、子ども達を応援しています。
塾では、新小学6年生を対象にした理科や社会の講義を週に1度行なっています。
特にこの時期、歴史に興味を持たせてあげられるかが大きな分岐点になります。
塾で説明を受けると、歴史に興味が出て、調べたくなってくるようです。
特に、歴史上の出来事だけでなく、その出来事が起こる因果関係を、詳しく説明してあげると、とても関心を持ち出します。
興味さえ持てば、子どもたちは趣味のように歴史の本を読み出します。
さらに、覚え方など教えると、覚え方にも感動してくれます。
どんなことも素直に吸収していけるこの時期に興味を持たせ、歴史が大好きになるようになればなあと思います。
中学・高校になって、楽しみながら勉強し、歴史が得意科目になるように、子ども達を応援しています。
2007年06月08日
10分間読書&国語読解の成果
10分間読書&国語読解の成果
国語の音読が大の苦手だったという小学2年生の生徒さんが、スラスラ音読ができるようになっています。算数の文章問題を絵や図を使って解くことで、逆に国語力がついてゆくのは当塾の特徴的な現象です。
今まであれほど勉強がきらいだった小学4年生の生徒さんが、夜、寝る前に1時間も読書するようになったという喜びの声もいただいています。
国語の音読が大の苦手だったという小学2年生の生徒さんが、スラスラ音読ができるようになっています。算数の文章問題を絵や図を使って解くことで、逆に国語力がついてゆくのは当塾の特徴的な現象です。
今まであれほど勉強がきらいだった小学4年生の生徒さんが、夜、寝る前に1時間も読書するようになったという喜びの声もいただいています。
2007年06月06日
イデア式算数文章題の成果
イデア式算数文章題の成果
現在、小学2年から6年までの子ども達が、複雑な算数文章問題を絵や図や表を駆使して、問題に取り組まれています。
特に最近、驚きを隠せないのが、家での勉強量の多さです。当塾では、「次の塾までにプリント3枚または3ページはやってこようね」というだけですが、多くの子ども達が、8ページ以上をしてこられます。中には40ページ以上する生徒もいます。
塾では一切、強制しない。押し付けもしない。なのに、子ども達は意欲を持って勉強をしてくるのです。さらに塾では、学校で習うような勉強の仕方はしません。もっぱら、見たこともない算数文章問題やパズル、さらに国語の読解問題をして、頭の鍛錬を中心にしています。
けれども、こうした鍛錬で、子ども達は、頭を使うことが好きになります。1時間もかけて解けたときの喜びは、快感だという生徒もいます。中には、1週間かけて1問を解く生徒もいます。「友達同士で、一緒に塾の宿題をするのだと言ってずっと勉強するようになったのです。それも本当に楽しそうだ。」と驚かれるお母さんが増えています。
現在、小学2年から6年までの子ども達が、複雑な算数文章問題を絵や図や表を駆使して、問題に取り組まれています。
特に最近、驚きを隠せないのが、家での勉強量の多さです。当塾では、「次の塾までにプリント3枚または3ページはやってこようね」というだけですが、多くの子ども達が、8ページ以上をしてこられます。中には40ページ以上する生徒もいます。
塾では一切、強制しない。押し付けもしない。なのに、子ども達は意欲を持って勉強をしてくるのです。さらに塾では、学校で習うような勉強の仕方はしません。もっぱら、見たこともない算数文章問題やパズル、さらに国語の読解問題をして、頭の鍛錬を中心にしています。
けれども、こうした鍛錬で、子ども達は、頭を使うことが好きになります。1時間もかけて解けたときの喜びは、快感だという生徒もいます。中には、1週間かけて1問を解く生徒もいます。「友達同士で、一緒に塾の宿題をするのだと言ってずっと勉強するようになったのです。それも本当に楽しそうだ。」と驚かれるお母さんが増えています。
2007年05月29日
懇談のタイミング
懇談のタイミング
新しく入塾された子ども達が塾に入ってから2〜3カ月も過ぎると、子ども達は様々な顔を見せてくれます。
私達が理解に苦しむ行動や発言をする子どももいれば、なかなか心を開いてくれなかったりする場合もあります。こんな時、私は懇談のチャンスと思って、保護者の方との個人懇談をさせていただきます。
その生徒の幼い頃からの話を聞かせていただくのです。すると、なぜそうした行動をとるのか、その生徒の心の痛みがわかってきます。
「そんな痛みをこの子は持っていたのかと思うとき、何もわからずに表面的に出会っていたことを申し訳なく思います。けれども、そんな子ども達の痛みをお母さん方から教えていただくことは、何にもまして有難いことと思っています。
そうした懇談の後、子ども達の勉強に向かう姿勢や私達との関わり等、すべてにおいて不思議と変化しているのです。教師の仕事とは、どれだけ子ども達の抱える痛みを自分の心に引き寄せられるかということかもしれないと思うこの頃です。
新しく入塾された子ども達が塾に入ってから2〜3カ月も過ぎると、子ども達は様々な顔を見せてくれます。
私達が理解に苦しむ行動や発言をする子どももいれば、なかなか心を開いてくれなかったりする場合もあります。こんな時、私は懇談のチャンスと思って、保護者の方との個人懇談をさせていただきます。
その生徒の幼い頃からの話を聞かせていただくのです。すると、なぜそうした行動をとるのか、その生徒の心の痛みがわかってきます。
「そんな痛みをこの子は持っていたのかと思うとき、何もわからずに表面的に出会っていたことを申し訳なく思います。けれども、そんな子ども達の痛みをお母さん方から教えていただくことは、何にもまして有難いことと思っています。
そうした懇談の後、子ども達の勉強に向かう姿勢や私達との関わり等、すべてにおいて不思議と変化しているのです。教師の仕事とは、どれだけ子ども達の抱える痛みを自分の心に引き寄せられるかということかもしれないと思うこの頃です。
2007年03月28日
この春休みの過ごし方について
この春休みの過ごし方について
ー新中1生及び保護者の方へー
小学校生活も終わり、いよいよ中学生活が始まると、ワクワクされている方も多いのではないかと思います。中学に入れば、クラブ活動があり、勉強も大変になる・・・
中学生活は、小学校とは全く違った生活が待っています。4月11日前後に入学式。そこから、授業も始まりますが、最初の授業はゆったりと進みます。勉強よりも中学に慣れることが大切にされます。
中学は小学校と違い、宿題もほとんど出されません。クラスの雰囲気はクラブ活動をどれにしようかという話題で持ちきりになります。
そして、すぐにゴールデンウイーク。クラブの仮入部が始まると、体育会系のクラブは、中1生は基礎体力作りをします。クラブが終わって帰宅すると、もう、クタクタ。新中1生にとって、この時の練習はかなりハードなんでしょう。食事をしたら、すぐに寝てしまう生活。特に朝の練習が始まると早朝に起きないといけないので、ますます勉強する時間は取りにくくなってきます。
最初の中間テストは5月18日〜20日前後。その一週間前にはテスト範囲の発表があります。テスト範囲が発表される頃から、テストまでに、各科目の先生方は、とても早いペースで授業を進めてゆきます。4月の頃とは大違いです。
さらに、学校配布のワークブックを各科目、宿題として答えあわせまでしてテスト当日までに提出するように指示する先生も多くいます。
このワークをそれまでにしていない生徒は、あわててやりだすのですが、そればかりしていると、テスト対策の勉強が間に合わなくなります。
けれども、ワークを提出しなければ、通知表が悲惨な成績になってしまいます。
提出物を出さなければ、いくらテストが良くても、通知表の結果は悪くなるのです。
また、最近の英語の授業は、リスニングが重視されてきているため、あまり単語の覚え方やヘボン式のローマ字の習得などに時間をかけていません。
しかし、テストは単語や英文を書けなければいけない。1学期が終わって、保護者の方から、「自分達の中学校の頃と全く違うことに驚いた」とよく言われます。
アルファベットやローマ字、さらにヘボン式のローマ字、そして中学で習う単語等を先に覚えていると、入学してからとても心強いものです。
このように、中学に入ってからの流れやシステムを少し知るだけで、この春休みや4月の過ごし方は変わってくるのではないでしょうか。
準備する心は未来を変えます。ぜひ、この春休みは、今できること、この春休みにしかできないことをされてはいかがでしょうか。
公式サイトもリニュアルしました。
一度ご覧下さい。
http://idea.gaias.net 続きを読む
ー新中1生及び保護者の方へー
小学校生活も終わり、いよいよ中学生活が始まると、ワクワクされている方も多いのではないかと思います。中学に入れば、クラブ活動があり、勉強も大変になる・・・
中学生活は、小学校とは全く違った生活が待っています。4月11日前後に入学式。そこから、授業も始まりますが、最初の授業はゆったりと進みます。勉強よりも中学に慣れることが大切にされます。
中学は小学校と違い、宿題もほとんど出されません。クラスの雰囲気はクラブ活動をどれにしようかという話題で持ちきりになります。
そして、すぐにゴールデンウイーク。クラブの仮入部が始まると、体育会系のクラブは、中1生は基礎体力作りをします。クラブが終わって帰宅すると、もう、クタクタ。新中1生にとって、この時の練習はかなりハードなんでしょう。食事をしたら、すぐに寝てしまう生活。特に朝の練習が始まると早朝に起きないといけないので、ますます勉強する時間は取りにくくなってきます。
最初の中間テストは5月18日〜20日前後。その一週間前にはテスト範囲の発表があります。テスト範囲が発表される頃から、テストまでに、各科目の先生方は、とても早いペースで授業を進めてゆきます。4月の頃とは大違いです。
さらに、学校配布のワークブックを各科目、宿題として答えあわせまでしてテスト当日までに提出するように指示する先生も多くいます。
このワークをそれまでにしていない生徒は、あわててやりだすのですが、そればかりしていると、テスト対策の勉強が間に合わなくなります。
けれども、ワークを提出しなければ、通知表が悲惨な成績になってしまいます。
提出物を出さなければ、いくらテストが良くても、通知表の結果は悪くなるのです。
また、最近の英語の授業は、リスニングが重視されてきているため、あまり単語の覚え方やヘボン式のローマ字の習得などに時間をかけていません。
しかし、テストは単語や英文を書けなければいけない。1学期が終わって、保護者の方から、「自分達の中学校の頃と全く違うことに驚いた」とよく言われます。
アルファベットやローマ字、さらにヘボン式のローマ字、そして中学で習う単語等を先に覚えていると、入学してからとても心強いものです。
このように、中学に入ってからの流れやシステムを少し知るだけで、この春休みや4月の過ごし方は変わってくるのではないでしょうか。
準備する心は未来を変えます。ぜひ、この春休みは、今できること、この春休みにしかできないことをされてはいかがでしょうか。
公式サイトもリニュアルしました。
一度ご覧下さい。
http://idea.gaias.net 続きを読む
2006年12月13日
教えるほどに「考えない子」になってゆく悪循環を考える−2

教えるほどに「考えない子」になってゆく悪循環を考える−2
……「考えることが大好きな子」への転換
こんな中で、私が到達したのが、今、塾で実践している指導でした。
今まで、子供たちは、中身が空っぽだから、私たち教師が手取り足取り教えていかなければいけないと思っていたのです。
けれども、どの子にも、無限の可能性がある。もうすでにそうした力を秘めていたのです。
そして先に子どもたちに教えることを辞めました。
子どもたちはもともと力を持っている。それを信じて引き出してあげたい。「子どもたちの自立を促す塾」これこそ、私の求める解答のように思いました。
私たちが教えるべきなのは、解き方ではなく、「試行錯誤の仕方」ではないかと思うようになりました。
決して解答や考え方やヒントも与えないで、自分の力で解けるようにしようと思いました。けれども、子どもたちは、文章を絵や図に直すこともしたことがない子がほとんどです。
だから最初、子どもたちに同伴し、絵や図の描き方の例を教えることも必要なことでした。しかし、子どもたちは、少しずつ、絵や図を書き出し、教えられなくても解けるまで自分でがんばれるようになってきたのです。
今、「考えることが大好きな子」「1問解くのに、30分でも1時間でも平気で考え続けられる子」「文章題が大好きな子」がたくさん誕生しています。
すべては、D君が私に教えてくれたことでした。「計算ばかりじゃ、つまらないよ」「いくら教えられて解いても、すぐに忘れちゃうよ」「もっとわくわくする勉強がしたい」そのような声なき声で、私に呼びかけ続けてくれたのだと思います。
2006年12月10日
教えるほどに「考えない子」になってゆく悪循環を考える−1

教えるほどに「考えない子」になってゆく悪循環を考える−1
D君は、小学校の2年生のときに入塾されたお子さんでした。
D君は計算も、文章題も、国語もみんな苦手なお子さんでした。
私は、D君が苦手な計算問題を、つまずいたところから教えていきました。そして、できるだけ、そばについて個人的に頻度良く見るようにしてゆきました。
確かに、少しずつ伸びてゆくのですが、勉強が好きになったり、自信がついていったりするわけではありませんでした。
なんとかしてあげたいと思って、教えれば教えるほどに、「考えない子」になってゆくのです。
わからないところを教えれば教えるほど「考えない子」が生まれる。
この矛盾は、私の長い間の謎でした。中学生以上になれば、まだ、それも効果があるのですが、小学生の間は、特に教えるほどに考えない子になってゆくように思いました。
私は、どうにかして、道がないものか、求めました。
さまざまな本を読んだり調べたりして、徐々にこのことは、私だけの悩みだけではないことがわかってきました。
世の中のお母さん方も、多くは、子どもに教えるほどに「考えない子」になっている悪循環で悩んでおられたのです。
<次号へ続く>