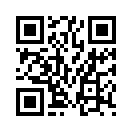2006年12月03日
絵本の読み聞かせのすすめ
絵本の読み聞かせのすすめ
私が20年間、塾で小学校1年から高校3年の子どもたちと接してきたことと、今、2歳と5歳の子どもを育てる中で、つながってきたことがあります。
それは、小さい頃の絵本の読み聞かせの偉大さ、本好きにすることの将来の可能性です。ふんだんに、様々な絵本を周囲に置いてやって、一日に3冊は読み聞かせをしてやること、そうした環境に子どもを置くと、本当に絵本好きになっていきました。そして教えなくても、絵本で学んだことと、実生活での体験が結びついてゆくのですね。
塾には、さまざまな子どもたちが入塾してきますが、本好きな小学生は、すごく吸収力がある子が多いと思います。小学校6年生で、中学1年の3学期に習う問題を初めて読むにも関わらず、中間・期末テストレベルの問題をパーフェクト近くに正解するので本当に驚いてしまいます。
小学生の間には、詰め込んで教えるより、本好きにしてあげること、好きな本を趣味のように読ませてあげることがいいと思います。特に絵本の読み聞かせなどは、小学校一年生で字が読めるようになったら、お母さんがやめてしまうケースが多いのですが、これはぜひ小学校3年生まで続けていただきたいです。
小学校の低学年では、自分で本を読んでいても、言葉をイメージ化する力がまだ備わっていません。読み手の気持ちや感情、イメージが子どもたちに伝わってゆきます。読んでいる方が、どのようなイメージで読んでいるかも、とても大きいのです。子どもたちは、そうした豊かな感情が伝わり、心を豊かにしてゆきます。そうしたことが国語の力、いえ、言葉をイメージに結ぶという、最もこの時期に引き出してあげないといけない力が身についてゆきます。
算数の文章題も、実は、そうした言葉をイメージ化し、絵や図になおすことから始まります。
勉強は無理やり教え込むものではなく、楽しいものなのだということを子どもたちが感じることが大切だと思います。子どもたちは、学びたがっています。そうした子どもたちのもともと、持っている可能性を引き出すことが、関わる大人たちの役割なのではと思っています。
2006年08月30日
イデア式算数文章題のススメ

子ども達に本当の「生きる力」を当塾で
養ってみませんか。
ステップ1.
保護者の方にオリエンテーションを行います。当塾の算数文章題がどのようなものか、その内容を説明させていただくと共に、お子さんにも実際に問題を解いていただき、その時のお子さんの表情を見ていただきたく思っています。
ステップ2.
お子さんに最も適したレベルを見つけるため、易しいものから順番に解いていただきます。子ども達は夢中になって問題を解いてゆきます。一問に20分〜30分考えるのは、どの子も当たり前になっています。解けたときの喜びは、お子さんの自信となり、どの子も本当に嬉しそうな顔をします。子ども達はどんどん、深く考え、自分の力で答えを出そうとするたくましさを身につけてゆきます。
ステップ3.
当塾の算数文章題は、単に算数の力をつけるだけでなく、国語読解力や、深く考える力、根気や集中力を養うメソッドです。どの子も、実は算数(考えること)が大好きなのです。もともとあったやる気をどんどん無くさせている原因が何かをぜひご理解いただければと思い、周りの大人が関わる時のルール等を説明させていただきます。
ステップ4.
2ヶ月ほど、塾での授業を経験していただいた後、保護者の方ともう一度、懇談をさせていただき、お子様の家庭での様子を伺い、塾での様子をお伝えします。
ステップ5.
算数文章題がペースに乗ってきたら、徐々に小学5年生あたりから、理科や社会のノートまとめの仕方、国語読解法などを指導してゆきます。
2ヶ月、3ヶ月と経つうちに、子ども達は大きな成長を遂げていると思います。
そして、1年もすると算数だけでなく、どの科目に対しても、どんな先生に対しても、問われた言葉を自分の心の中でイメージ化し、絵や図に置き換えて、そのイメージを動かせるような思考をするようになってゆきます。そうすると、どんなに複雑な問題であっても、まず自分で条件を整理し、試行錯誤して、解いてみようという子になっていることでしょう。
これからの時代、いつどんな試練が起きるかわかりません。
そんなときに、試練に対して、投げたり、あきらめたりすることなく、試行錯誤して、自分なりの解答を考え出せるならば、これは、一生の宝だと思います。たかが算数、されど算数です。
子ども達に本当の「生きる力」を当塾で養ってみませんか。
2006年08月25日
イデア式小学英語学習のステップ

小6までにぜひ、英語の単語の持つ大原則を
マスターしていきましょう。
ステップ?.楽しく、ローマ字の読み書きができるようにします。
ステップ2.ヘボン式のローマ字が自由に使いこなせるようにします。
ステップ3.英語特有の発音とつづりの関係をわかりやすく体得していきます。
ステップ4.中学1年の英単語の読み書きを無理なく、覚えていきます。
ステップ5.中学1年の英語テキストの本文を楽しく暗唱し、書けるようにしていきます。
これにより、今まで、何十回と書かないと新出単語を覚えられなかった子達が、数回程練習するだけで、ほとんど覚えてしまうことができるようになってきました。
中学では、上記、1〜5のステップをほとんど行わずに教科書に入ってしまうため、英語を読めず、書けない子ども達が増えてしまうのです。小6までにぜひ、当塾で英語の単語の持つ大原則をマスターしていきましょう。
2006年08月15日
小学生の子どもたちを地図好きに!


小学生の子どもたちを地図好きに!
中学生で地理を習った時に地理が苦手になる理由は、
国名や、県名を覚えていないことがあげられます。
100円ショップのダイソーに、100円でお風呂場に貼れる
「にほんちず」が売られているのをご存知ですか?
すべてひらがなで書かれてあって、
これを貼っているといつの間にか県名を覚えてしまう子が多いそうです。
また、ちょっと細かいもので、1000円前後でもお風呂に貼れる地図もあります。
テストに出るからその時に覚えるのでは、面白くありません。
興味を持って、楽しんで覚えるのが一番。苦手な方にはおススメです。
2006年08月11日
勉強と人生を一つに結ぶために……

勉強と人生を一つに結ぶために、
私たち大人がやるべきこと。とやってはいけないこと
小学生の難しい算数の文章題や、
中学数学の複雑な応用問題を解かせるのと、
人生で出会う様々な試練は、
本当に等しいように思っています。
当塾では子どもたちにこうした難問を解いてもらうとき、
ほとんど教えないようにしています。
子どもたちはうんうん唸って、
問題とにらめっこしています。
小学生の場合は、問題を解くことに楽しんでくれていますが、
中学生から塾に入った生徒などは、
こうした複雑な文章題に慣れていないため、
初めはすぐに、あきらめたり、
少し考えてわからなくなると怒り出したり、
すねてしまったり、人と比較して一喜一憂したり・・・
様々な反応を示します。
こうした難問に出会った時も、
子どもたちが人生における試練に出会ったときも、
同じような反応をしているのではないかと思うのです。
試練に出会う。
その時に心の中は誰もが葛藤を起こします。
けれども葛藤するにも、
否定的な葛藤(あきらめや投げやりな思い、怒りや自己満足など)と、
前向きな葛藤があるのではないかと思うのです。
前向きな葛藤は、試行錯誤をしてゆきます。
こうした試行錯誤をして、様々にやり方を考える時に、
ある時、正解にたどりつくのです。
その時に内から溢れてくる歓びはたとえようがありません。
その子だけの宝物です。そしてその歓びに味をしめると、
子どもたちは
「自分だって、すてたものじゃない。やればできるんだ」
と思うようです。
いくら時間がかかってもいいんです。
むしろ、すぐに解けてしまう問題をいくらやっても、
あまり力は付きません。
「考える価値のある問題」をじっくり丁寧に、
考える時間を持てば、思考力がついてゆくのです。
このようにして関わってゆくと
少しずつですが、子どもたちに、こらえ性ができてきます。
粘りのある子に育てたい。
そして、試練に強い子どもに育てたい。
人生の試練も勉強も、
子どもたちは自分の力で解決したがっているのです。
保護者という枠を越えて
同伴者、メンターとして
試練に立ち向かえる子どもたちを育んでいきませんか?
2006年08月08日
英語の暗唱から知った子どもたちの可能性の凄さ

英語の暗唱から知った子どもたちの可能性の凄さ
塾をし始めて、まもない頃、ものすごく驚いたことがあります。
それは中学1年生の夏休みに9人ほどのクラスで、
中学1年の英語の教科書を
暗唱してもらったときのことです。
このクラスは中1に入る前の3月の春休みから、
教科書の暗唱を1学期の間、
ずっと教科書の暗唱と単語の暗記を中心に行っていました。
ほとんどが、1ページずつの暗唱です。
たまに1レッスンずつの暗唱を通してさせたりもしていました。
ほとんどの生徒に教科書の単語と本文を日頃、
暗記してもらっていたのですが、
この日は総まとめという意味で、順番に教科書の初めから、
暗唱してくださいと言いました。
一人目のT君は、レッスン1からとうとう、
教科書の最後までを実に20分かけて言い続けたのです。
次のH君も同じでした。
その次のDさんも・・・。
それは本当にすごい光景でした。
暗唱できた生徒は、ノートにすらすらと
教科書の本文を書くテストをしていました。
「この子たちは、教科書を自分でつくれるんだ!」
私は、この時期の子どもたちがいかに暗記力があるのか、
人間の力の可能性を見せていただいたように思いました。
2006年08月04日
理科好き、社会好きな子にするのは……

理科好き、社会好きな子にするのは
学研の「ひみつシリーズ」がおすすめ
以前、ものすごく、理科の知識が豊富な男の子が塾にいました。
その子は、中学3年間、ずっと理科と社会が「5」をとるんですが、
特に勉強をしていなくても、理科と社会は「5」なんですね。
授業で教える前にいろいろと知っていて、どうしてそんなに博識なのか、
その子に聞いたことがありました。
すると、小学校の時に図書館で、いつも学研の学習まんが
「人体のひみつ」などの「○○のひみつ」というシリーズばかり
好きで読んでいただけです。と言っていました。
同じように、社会の歴史がものすごく得意な生徒も、
やはり、ルーツを遡ると、みんな小学校の時に歴史のまんがばかり
読んでいたというんですね。
何がいいのかと言うと、歴史上の人物が漫画ではっきりと
イメージで覚えてしまうからなのだそうです。
だから、教科書で習った時に、
「先生の説明がはっきりと漫画や映像ででてくるのだ」
と言っています。
かくいう私も、小学校の頃、こうした学習まんがが大好きでした。
でも、今の漫画の方が、はるかに絵が上手で人物の特徴が出ています。
私たち親ももう一度、子どもの頃に戻って
お子さんと一緒に、学習まんがを楽しんで見てはいかがですか
意外と、あーそうだったのか!と
科学や歴史は、私たちが勉強していた時から
新たな発見や修正が至る所で加えられています。
目からウロコの新事実も、「ひみつシリーズ」で
見つかるかもしれませんよ!

2006年07月31日
子どもたちの可能性を開くために……

子どもたちの可能性を開くために……
私は長年、塾をしていて、中学1年生の頃に入塾して来る子どもたちに対して
いつも疑問に感じていたことがありました。
それは、同じことを聞いて、どうしてこんなに吸収力の違いがあるのかということでした。
その違いは、大きくは国語力、読解力の違いであることは感じていたのですが、
それでも、国語ができて数学の複雑な文章問題ができない生徒がいるのはなぜなのかと思っていました。
その理由をいろいろ調べていくうち、言葉をイメージすることができる能力が育っているかどうかが、
決定的であることがわかってきました。
ここから生まれた算数の文章問題を通しての授業は
子どもたちに劇的な変化を与えてゆきました。
さらに、中学生の数学の指導についても、同じ問題を使っていても、
教師の指導の仕方で、全く伸び方が変わってくることが、最近わかってきました。
もちろん、私よりも、もっと上手な教え方の先生方は山のようにおられることと思います。
しかし、子どもたちが、短時間にわくわくしながら、問題の本質をつかみ、
思考力がつくのは、教師の側、特に子どもに対する思い方に
大きな影響があると思えてならないのです。
それは、一言で言うなら、
「子どもたちには、ものすごい可能性がある」
という確信があるかどうかのように思うのです。
私は以前、「子どもたちは何もわかっていないから、教えてあげないといけない」
とずっと思っていました。
しかし、その前提がある限り、子どもたちはどうやっても、伸びていかないし、
子どもたちはどんどん、疲弊していくのです。
それを、子どもたちには、誰にも考える力があるんだと思って、
授業をすると、本当に子どもたちが自分で発見するまで「待つ」ことが
できるようになりました。
そして、適切なヒントを
適切な時期に与えられるようになってきました。
まだまだ、私も発展途上の人間ですが、
子どもたちから毎日いろいろな気づきを教えていただいています。
2006年07月29日
一つのヒント、一つの問いかけで…

一つのヒント、一つの問いかけで、
子どもたちの未来は変わる
今日も、保護者懇談がありました。
ある小学生のお子さんは、当塾に入るまで、
一切、算数の文章題を解くことがなかったそうです。
しかし、塾に入ってから、最近は親に分からない問題を聞くことが
なくなりました。との事。
算数の文章題を解くときも絵や図も書けるようになっているし、
塾に行くのが本当に嬉しいみたいで、
いつも30分前から行く用意をして、待っているんですとの事。
塾に仲良しの友達が来ているわけでもないのに、本当に不思議です。
この前も、丸々1時間、一つの文章問題を解こうとしてがんばっていました。
終了間際に解くことができて、嬉しそうな顔を見るのは本当に、
私どもにすれば格別な思いです。
こんな子ども達がたくさん増えればいいなあと思います。
2006年07月28日
当塾でお勧めの3冊をご紹介します

当塾でお勧めの3冊をご紹介します
私たちの塾では、小学生も中学生も授業の最初に、いろいろな人の伝記を読んで、
感想を書いてもらっています。その中で、お勧めの3冊をご紹介します。
まず一つは「ヘレンケラー」、そして「マザーテレサ」「ジャンヌ=ダルク」です。
すべて、講談社火の鳥伝記文庫です。
これは、私が多くの子ども達の感想文を読む中で、この3冊を読んでいるときの
子ども達の感想に、私自身が感動してしまうからです。
共通して言えるのは、自分のことを横に置いても他人のことや世界の問題に対して、
何とかしようとする生き様が、子ども達を感動に結ぶようです。
勉強をただ、自分の点数をあげて自分がほめてもらうとかのためではなく、
「世の中の役に立ちたい」そのために、自分も何かできることをしたい、
また、役に立てる自分になりたいと思う時、
子ども達は、勉強に対しての考え方を変えていっているような気がします。
自分を成長させ、他人のためになれる自分になるために、
勉強しようと発心するのです。私はこうした子ども達を見て、
本当に素晴らしいなあ、と思えてなりません。
ぜひ、お子さん方に読んでみていただきたいと思います。