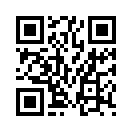2008年11月21日
これは言わないで! NG集 その3
これは言わないで! NG集 その3
・「○○高校くらい行けなかったらどうするの。」というのもNGです。
この言葉の奥に「恥ずかしい。世間体が悪い。近所の人に何て思われるか」という思いがあったら、絶対NGです。子どもたちは、世間体のために高校に行くんだな、というお母さんの思いをストレートに受けとめます。人に馬鹿にされないために勉強というものや高校というものがあるんだと思うでしょう。お母さんの見栄のために自分は勉強をさせられているんだと思うことでしょう。いったん、そのフレージングを持ってしまうと、「親のために勉強をさせられているかわいそうな私」というスタンスとなり、苦しくなると、人のせいにして、自分で道を切り開けない子どもになってしまいます。勉強ができないだけでなく、将来、嫌なことがあったらすぐにくるりと背を向けて、逃げてゆく「生きる力」のない子どもになってしまいます。
・「ちゃんとしなさい。」「しっかりしなさい。」「頼りないなあ」はNGです。
この言葉の奥に「できなければだめ」という思いがあるかもしれないからです。子どもたちは、できなければ価値がない、すなわちできる・できないで人間の価値が決まると刷り込まれるでしょう。大切なのは、できない自分でも存在自体が大切で尊ばれているというメッセージです。その気持ちを深く抱いた子どもは、精神が安定します。愛されているという実感が、子どもたちを成長の土台です。完成された人間などいないと思います。誰もが発展途上であり、未熟を抱えた存在であることを認めながら、それでも最高の努力をしつつ、成長する過程にこそ輝きがあるのではないかと思います。ここで、誤解を避けたいのは、できることがいけないということではありません。可能性を引き出すために、可能性を阻む言葉を避けていただきたいということです。
・「○○高校くらい行けなかったらどうするの。」というのもNGです。
この言葉の奥に「恥ずかしい。世間体が悪い。近所の人に何て思われるか」という思いがあったら、絶対NGです。子どもたちは、世間体のために高校に行くんだな、というお母さんの思いをストレートに受けとめます。人に馬鹿にされないために勉強というものや高校というものがあるんだと思うでしょう。お母さんの見栄のために自分は勉強をさせられているんだと思うことでしょう。いったん、そのフレージングを持ってしまうと、「親のために勉強をさせられているかわいそうな私」というスタンスとなり、苦しくなると、人のせいにして、自分で道を切り開けない子どもになってしまいます。勉強ができないだけでなく、将来、嫌なことがあったらすぐにくるりと背を向けて、逃げてゆく「生きる力」のない子どもになってしまいます。
・「ちゃんとしなさい。」「しっかりしなさい。」「頼りないなあ」はNGです。
この言葉の奥に「できなければだめ」という思いがあるかもしれないからです。子どもたちは、できなければ価値がない、すなわちできる・できないで人間の価値が決まると刷り込まれるでしょう。大切なのは、できない自分でも存在自体が大切で尊ばれているというメッセージです。その気持ちを深く抱いた子どもは、精神が安定します。愛されているという実感が、子どもたちを成長の土台です。完成された人間などいないと思います。誰もが発展途上であり、未熟を抱えた存在であることを認めながら、それでも最高の努力をしつつ、成長する過程にこそ輝きがあるのではないかと思います。ここで、誤解を避けたいのは、できることがいけないということではありません。可能性を引き出すために、可能性を阻む言葉を避けていただきたいということです。
2008年11月19日
これは言わないで! NG集 その2
・「勉強しなさい」と言って、親はテレビやレンタルビデオを見ている。これはNG。
子どもに勉強させたいなら、お父さんやお母さんは音や映像を消さないといけません。一緒に、横でご自分の本を読まれたり、ご自身の勉強をされることが、一番大切です。子どもは親の後姿を真似しているだけなのですから。
・「ね。だから言ったでしょ。わかった?。」はNGです。
この言葉の奥には「どう。私(お父さんまたはお母さん)はすごいでしょう。」という優位の思いであったり、「どうだ、まいったか。私は正しい」というどちらが正しいかを決めて、「相手をやり込めることが価値のあること」という価値観を子どもに植え付けてしまいます。どちらの場合も、子どもたちは、友達に対して、同じように話をし、人間関係をつくってゆくでしょう。前者の場合であれば、「私はできる。」という見方をし、友達を見下すことになり、友達からは反感をもたれるために、友達が離れてしまうことになってしまいます。後者の場合であれば、常に人間関係は闘いであり、言い負かされたらおしまいと思って、相手がまいったというまで人を責め続けることになります。そうすると、都合の悪いことがあると人のせいにしてしまい、自分で責任を負うことができず、自分には非がなかったということだけ、正しさの主張だけに人生を費やしてしまうことになりかねないかもしれません。
子どもに勉強させたいなら、お父さんやお母さんは音や映像を消さないといけません。一緒に、横でご自分の本を読まれたり、ご自身の勉強をされることが、一番大切です。子どもは親の後姿を真似しているだけなのですから。
・「ね。だから言ったでしょ。わかった?。」はNGです。
この言葉の奥には「どう。私(お父さんまたはお母さん)はすごいでしょう。」という優位の思いであったり、「どうだ、まいったか。私は正しい」というどちらが正しいかを決めて、「相手をやり込めることが価値のあること」という価値観を子どもに植え付けてしまいます。どちらの場合も、子どもたちは、友達に対して、同じように話をし、人間関係をつくってゆくでしょう。前者の場合であれば、「私はできる。」という見方をし、友達を見下すことになり、友達からは反感をもたれるために、友達が離れてしまうことになってしまいます。後者の場合であれば、常に人間関係は闘いであり、言い負かされたらおしまいと思って、相手がまいったというまで人を責め続けることになります。そうすると、都合の悪いことがあると人のせいにしてしまい、自分で責任を負うことができず、自分には非がなかったということだけ、正しさの主張だけに人生を費やしてしまうことになりかねないかもしれません。
2008年11月16日
これは言わないで! NG集 その1
これは言わないで! NG集 その1
・「早くしなさい!」これはNG。
この言葉の奥には「早くすることが大切。遅いことは価値がないこと。」という気持ちが伝わるかもしれません。大人からすれば、そういうつもりはなくても、子どもたちは言葉の奥にある思いを敏感に感じ取ります。早くしなさいといわれ続けた子どもは、言われるまで、何もしません。さらに、言われた時だけ、あせって、早くすることだけを考えています。あせってパニックを起こしてしまう子に育ってしまいます。急がなくても「ゆっくり、じっくり、ていねいに」をモットーに行なうことを教えましょう。
・「こんな問題も解けないの?」「こんなこともわからないの?」はNG。
この言葉の奥には、「この程度の問題は解けて当然。あなたは、当然のこともできない基準以下の人間である。」というメッセージが伝わってしまいます。子どもにとれば、これほど自分の存在が「生きる意味のない存在。価値のない人間」という受けとめ方をしてしまうかもしれません。解けないには解けない原因があります。特に、算数の応用問題や文章題などは、学校でいきなり式をたてることを要求されるため、子どもたちは頭の中で、文章をイメージ化させようとします。それは、脳が発達段階の小学生のうちは、してはいけないことだと思います。文章を一文一文、どういうことを書いてあるのかを絵や図に直してゆくことから始めましょう。解けなくても、考える力をこのようにして引き出してあげることができます。そして、自分の力で発見して解けた時、どれほどの自信につながるでしょうか。子どもは信じられてこそ、可能性を引き出すことができるのではないでしょうか。
・「早くしなさい!」これはNG。
この言葉の奥には「早くすることが大切。遅いことは価値がないこと。」という気持ちが伝わるかもしれません。大人からすれば、そういうつもりはなくても、子どもたちは言葉の奥にある思いを敏感に感じ取ります。早くしなさいといわれ続けた子どもは、言われるまで、何もしません。さらに、言われた時だけ、あせって、早くすることだけを考えています。あせってパニックを起こしてしまう子に育ってしまいます。急がなくても「ゆっくり、じっくり、ていねいに」をモットーに行なうことを教えましょう。
・「こんな問題も解けないの?」「こんなこともわからないの?」はNG。
この言葉の奥には、「この程度の問題は解けて当然。あなたは、当然のこともできない基準以下の人間である。」というメッセージが伝わってしまいます。子どもにとれば、これほど自分の存在が「生きる意味のない存在。価値のない人間」という受けとめ方をしてしまうかもしれません。解けないには解けない原因があります。特に、算数の応用問題や文章題などは、学校でいきなり式をたてることを要求されるため、子どもたちは頭の中で、文章をイメージ化させようとします。それは、脳が発達段階の小学生のうちは、してはいけないことだと思います。文章を一文一文、どういうことを書いてあるのかを絵や図に直してゆくことから始めましょう。解けなくても、考える力をこのようにして引き出してあげることができます。そして、自分の力で発見して解けた時、どれほどの自信につながるでしょうか。子どもは信じられてこそ、可能性を引き出すことができるのではないでしょうか。
2008年11月08日
お子さんが元気にイキイキになる接し方5
お子さんが元気にイキイキになる接し方5
魔法のアクションクリプト
●将来の夢を語り合える親子関係をつくりましょう
子どもが家で勉強をしないことを、人のせいにしたり、もっと強制的に勉強をするように言って欲しいと言われる保護者の方もおられます。しかし、子どもが勉強しない環境を作ったのは、ご家庭なのです。一番の原因が家庭であるならば、その原因を取り除けば、子どもは勉強をするようになります。
例えば、点数ばかりに目がいって、結果を出さなければ子どもを叱るのは、大きな間違いです。考えることの楽しさや、自分で発見することの喜びや、結果よりも過程を大切にする関わりをされていたら、子どもたちは結果よりも、考えること、意味を知ること、発見すること、過程を知ることに重心が移ってゆきます。そんな子ども達は、勉強する時間や、考える時間、読書をする時間を楽しみとなり、それは自ずと、結果に現れてきます。さらに、中学生にもなると、子どもたちは意思が芽生えてきます。その意思を尊重し、将来の夢を語り合える親子関係ならば、子どもは、将来の夢と勉強がつながってゆき、勉強する必然を感じるのではないでしょうか。
そのような、関わりをぜひ、保護者の皆様、子ども達と作ってください。そして、行きたい高校を見つけ、その学校に足を運び、リアリティを持たせましょう。同時に、模擬テストを積極的に受験し、自分の今の学力でいけるかどうかを把握させましょう。現実を直視し、目標を持つ。こうした動機付けは、まさにお母さん方がその気になれば、いつからでもできることなのではないかと思います。
魔法のアクションクリプト
●将来の夢を語り合える親子関係をつくりましょう
子どもが家で勉強をしないことを、人のせいにしたり、もっと強制的に勉強をするように言って欲しいと言われる保護者の方もおられます。しかし、子どもが勉強しない環境を作ったのは、ご家庭なのです。一番の原因が家庭であるならば、その原因を取り除けば、子どもは勉強をするようになります。
例えば、点数ばかりに目がいって、結果を出さなければ子どもを叱るのは、大きな間違いです。考えることの楽しさや、自分で発見することの喜びや、結果よりも過程を大切にする関わりをされていたら、子どもたちは結果よりも、考えること、意味を知ること、発見すること、過程を知ることに重心が移ってゆきます。そんな子ども達は、勉強する時間や、考える時間、読書をする時間を楽しみとなり、それは自ずと、結果に現れてきます。さらに、中学生にもなると、子どもたちは意思が芽生えてきます。その意思を尊重し、将来の夢を語り合える親子関係ならば、子どもは、将来の夢と勉強がつながってゆき、勉強する必然を感じるのではないでしょうか。
そのような、関わりをぜひ、保護者の皆様、子ども達と作ってください。そして、行きたい高校を見つけ、その学校に足を運び、リアリティを持たせましょう。同時に、模擬テストを積極的に受験し、自分の今の学力でいけるかどうかを把握させましょう。現実を直視し、目標を持つ。こうした動機付けは、まさにお母さん方がその気になれば、いつからでもできることなのではないかと思います。
2008年11月03日
お子さんが元気にイキイキになる接し方4
お子さんが元気にイキイキになる接し方4
魔法のアクションクリプト
●本の読み聞かせは、小3までは続けましょう。
本の読み聞かせは、小3までは続けましょう。絵本の読み聞かせを、小学校で字を覚えたときからしなくなるお母さん方も多いのですが、これは、とてももったいないことです。子どもは字を読めるようになったとしても、言葉の意味やイメージを持つことがまだ十分ではありません。言葉は、読み手の持つイメージが、子ども達に広がってゆくからです。ですから、お母さんの読み聞かせこそ、子ども達の想像力、思考力を引き出し、心を豊かにすることのできる大切な時となるからです。
●一生懸命努力しているところを見つけてあげてください。そしてそれを誉めてあげましょう
私達は、どうしても子どもを見下げて、ああしなさい、こうしなさいと指示し、早くさせよう急がせてしまいがちです。そうなると子どもは、だんだん「指示待ち人間」となり、依存的になってゆきます。自分で考えようとしないために、ますます言われないとしない子どもになってゆきます。そういう姿を見て、さらに威圧的に関わったり、子どもを責めたりし、悪循環に陥るご家庭は多いのではないでしょうか。しかし、子どもたちは、本当は私達や親に応えようと懸命です。その姿を見つけようとすることがどれほど大切なことでしょうか。けなげに一生懸命努力しているところを見つけてあげてください。そしてそれを誉めてあげましょう。子どもが本当にしたいことを大切にしてあげていただきたいのです。
魔法のアクションクリプト
●本の読み聞かせは、小3までは続けましょう。
本の読み聞かせは、小3までは続けましょう。絵本の読み聞かせを、小学校で字を覚えたときからしなくなるお母さん方も多いのですが、これは、とてももったいないことです。子どもは字を読めるようになったとしても、言葉の意味やイメージを持つことがまだ十分ではありません。言葉は、読み手の持つイメージが、子ども達に広がってゆくからです。ですから、お母さんの読み聞かせこそ、子ども達の想像力、思考力を引き出し、心を豊かにすることのできる大切な時となるからです。
●一生懸命努力しているところを見つけてあげてください。そしてそれを誉めてあげましょう
私達は、どうしても子どもを見下げて、ああしなさい、こうしなさいと指示し、早くさせよう急がせてしまいがちです。そうなると子どもは、だんだん「指示待ち人間」となり、依存的になってゆきます。自分で考えようとしないために、ますます言われないとしない子どもになってゆきます。そういう姿を見て、さらに威圧的に関わったり、子どもを責めたりし、悪循環に陥るご家庭は多いのではないでしょうか。しかし、子どもたちは、本当は私達や親に応えようと懸命です。その姿を見つけようとすることがどれほど大切なことでしょうか。けなげに一生懸命努力しているところを見つけてあげてください。そしてそれを誉めてあげましょう。子どもが本当にしたいことを大切にしてあげていただきたいのです。
2008年10月31日
お子さんが元気にイキイキになる接し方3
お子さんが元気にイキイキになる接し方3
魔法のアクションクリプト
●同じ高さの目線で話をしましょう
お子さんと同じ高さの目線で話をしましょう。そうすることで、子どもたちは、心を開いてくれます。上からの目線では、威圧的になってしまい、子どもは心を閉ざしてしまいます。私たちも、塾で子ども達を一人一人見て回りながら、わからないところを説明する時、目の高さをあわせて質問したり教えたりします。なかなかそうできないことも多いのですが、これを意識することが、なかなか難しいことであることがわかります。お母さんも、お子さんの目線になって話をすることに、挑戦してみてください。そして、子どもの心の声を聞くようにしましょう。今までに聞こえなかったものが聞こえるかもしれません。
●子どもは、いつも何でも学びたがっています
「子どもは、いつも学びたがっている。」ということを心に置いていただきたいと思います。机の上でドリルや問題集をしている時だけが勉強のように錯覚される方も多くおられますが、テレビや家族の会話や、町を歩いている時でも、子どもたちは、「これってどういうこと?」「なぜそんな風にするの?」と聞いてくる場合があります。そんな時、子どもの目の前に映像が出てくるように、説明してあげることが保護者の方の役割です。その機会が増えれば増えるほど、子ども達の可能性は広がってゆきます。
●勉強した後は、必ず机の上には何も置いていない状態になるよう、習慣づけてあげましょう
勉強した後は、必ず机の上には何も置いていない状態になるよう、習慣づけてあげましょう。何もなくて気持ちのいい感覚を味わわせてあげることが大切です。そして、物事には必ず起承転結があり、スッキリと終わった状態になるように、習慣づくまでは、横でお母さんがついてあげていただければと思います。そして、片付けた後は、ぜひ褒めていただきたいと思います。
魔法のアクションクリプト
●同じ高さの目線で話をしましょう
お子さんと同じ高さの目線で話をしましょう。そうすることで、子どもたちは、心を開いてくれます。上からの目線では、威圧的になってしまい、子どもは心を閉ざしてしまいます。私たちも、塾で子ども達を一人一人見て回りながら、わからないところを説明する時、目の高さをあわせて質問したり教えたりします。なかなかそうできないことも多いのですが、これを意識することが、なかなか難しいことであることがわかります。お母さんも、お子さんの目線になって話をすることに、挑戦してみてください。そして、子どもの心の声を聞くようにしましょう。今までに聞こえなかったものが聞こえるかもしれません。
●子どもは、いつも何でも学びたがっています
「子どもは、いつも学びたがっている。」ということを心に置いていただきたいと思います。机の上でドリルや問題集をしている時だけが勉強のように錯覚される方も多くおられますが、テレビや家族の会話や、町を歩いている時でも、子どもたちは、「これってどういうこと?」「なぜそんな風にするの?」と聞いてくる場合があります。そんな時、子どもの目の前に映像が出てくるように、説明してあげることが保護者の方の役割です。その機会が増えれば増えるほど、子ども達の可能性は広がってゆきます。
●勉強した後は、必ず机の上には何も置いていない状態になるよう、習慣づけてあげましょう
勉強した後は、必ず机の上には何も置いていない状態になるよう、習慣づけてあげましょう。何もなくて気持ちのいい感覚を味わわせてあげることが大切です。そして、物事には必ず起承転結があり、スッキリと終わった状態になるように、習慣づくまでは、横でお母さんがついてあげていただければと思います。そして、片付けた後は、ぜひ褒めていただきたいと思います。
2008年10月27日
お子さんが元気にイキイキになる接し方2
お子さんが元気にイキイキになる接し方-2
●お子さんのこと、心から喜んであげてください。
お子さんが何かできるようになったり、成功体験を得たり、壁を乗り越えた時は、「良かったねえ。すごいじゃない。」と心から喜んであげてください。できれば、そのことを、お子さんの前でご主人に伝えてあげてください。親子で成長を喜び、歓びの循環を起こしてゆくことは、お子さんの自信にもつながりますし、次への意欲につながってゆきます。
●お母さんが勉強を教えなくてもかまいません。まず、受けとめてあげましょう
中学生で、テストで結果が思うように出なかったときこそ、「今回はどうしたのかな。点数を見てどう思った?ショックだったんだね。」とまず受けとめてあげましょう。
良かったところもあれば、「直前はよく頑張ったじゃない。○○の科目は良かったじゃない」などと伝え、足りなかったところがあれば、「何が原因だったんだろう?自分ではどう思う?」と本人の口から聞いてあげましょう。本人が具体的に、次回はどうしたらよいと思うかを聞いてあげて、実際にどういう風に勉強をするつもりなのかを紙に書かせてあげましょう。
さらに、わからないところは、ノートに解答や解説まで貼り付けて、塾の先生や、学校の先生の中で、聞きやすい先生に、説明してもらいましょう。これを毎回、繰り返すだけで、必ず伸びてゆきます。お母さんが教えなくてもかまいません。わからないところを先生に一つひとつ質問し、解消してゆくことが一番伸びてゆきます。
●小学生では、テストの点数で一喜一憂することは避けましょう。
子ども達が勉強をじっくり取り組んでいるか、間違ったところはどう考えていたのか、意味がわからないところがあれば、それをノートに貼って、先生に質問するようにしてみましょう。親が教えるより、学校の先生に教えてもらうほうが、質問の癖がつき、質問上手な子になってゆきます。
●お子さんのこと、心から喜んであげてください。
お子さんが何かできるようになったり、成功体験を得たり、壁を乗り越えた時は、「良かったねえ。すごいじゃない。」と心から喜んであげてください。できれば、そのことを、お子さんの前でご主人に伝えてあげてください。親子で成長を喜び、歓びの循環を起こしてゆくことは、お子さんの自信にもつながりますし、次への意欲につながってゆきます。
●お母さんが勉強を教えなくてもかまいません。まず、受けとめてあげましょう
中学生で、テストで結果が思うように出なかったときこそ、「今回はどうしたのかな。点数を見てどう思った?ショックだったんだね。」とまず受けとめてあげましょう。
良かったところもあれば、「直前はよく頑張ったじゃない。○○の科目は良かったじゃない」などと伝え、足りなかったところがあれば、「何が原因だったんだろう?自分ではどう思う?」と本人の口から聞いてあげましょう。本人が具体的に、次回はどうしたらよいと思うかを聞いてあげて、実際にどういう風に勉強をするつもりなのかを紙に書かせてあげましょう。
さらに、わからないところは、ノートに解答や解説まで貼り付けて、塾の先生や、学校の先生の中で、聞きやすい先生に、説明してもらいましょう。これを毎回、繰り返すだけで、必ず伸びてゆきます。お母さんが教えなくてもかまいません。わからないところを先生に一つひとつ質問し、解消してゆくことが一番伸びてゆきます。
●小学生では、テストの点数で一喜一憂することは避けましょう。
子ども達が勉強をじっくり取り組んでいるか、間違ったところはどう考えていたのか、意味がわからないところがあれば、それをノートに貼って、先生に質問するようにしてみましょう。親が教えるより、学校の先生に教えてもらうほうが、質問の癖がつき、質問上手な子になってゆきます。
2008年10月24日
お子さんが元気にイキイキになる接し方1
魔法のトークスクリプト
☆こういう声がけをしてあげてくださいませんか!
お子さんが元気にイキイキになる接し方-1
●「おはよう。」「いってらっしゃい。」「お帰り。」など、日常の挨拶をしましょう。
できれば、満面の笑みと、「あなたが大好き」という思いを込めて、声がけしてみませんか。
●「〜しましょう。」「〜 しようか」といいましょう。
子ども達を上からの目線でとらえなければ、子どもは、生き生きと主体的に生きることができるようになります。
●「あなただったら、絶対できるよ。」と声をかけてあげてください。
お子さんが自信を失っているようだったら、ぜひ、「あなただったら、絶対できるよ。」と声をかけてあげてください。
子どもたちは周囲の大人に信じられていると実感することで、「自分もやればできるのかもしれない」と思うことができます。
☆こういう声がけをしてあげてくださいませんか!
お子さんが元気にイキイキになる接し方-1
●「おはよう。」「いってらっしゃい。」「お帰り。」など、日常の挨拶をしましょう。
できれば、満面の笑みと、「あなたが大好き」という思いを込めて、声がけしてみませんか。
●「〜しましょう。」「〜 しようか」といいましょう。
子ども達を上からの目線でとらえなければ、子どもは、生き生きと主体的に生きることができるようになります。
●「あなただったら、絶対できるよ。」と声をかけてあげてください。
お子さんが自信を失っているようだったら、ぜひ、「あなただったら、絶対できるよ。」と声をかけてあげてください。
子どもたちは周囲の大人に信じられていると実感することで、「自分もやればできるのかもしれない」と思うことができます。
2008年08月16日
夏休みと二学期からの勉強の仕方のアドバイス 自己啓発編
夏休みと二学期からの勉強の仕方のアドバイス
勉強方法も大切ですが、一番大切なのは、本人の気持ちだと思います。特に、志望高校が早く決まり、「どうしてもその学校に行きたい。その学校の生徒になっているイメージがつかめている」生徒は、何をするにも意欲が違います。
私は、ぜひ、様々な高校に見学に行くことをおすすめします。それが、行きたくない学校であっても、一度実際に、足を運んで、行ってみることが大切と思います。そうすると、「ここは、合わない。ここには行きたくない」とか、「こんなクラブがあるのか。雰囲気がすごくすてきだ。自分はこの学校に行きたい」などと思うかもしれません。学校の雰囲気とは、恐ろしいもので、空気のように流れているものです。それはうそがつけません。そして、直感的に、合うかどうかもわかったりするのではないでしょうか。
ぜひ、様々な学校に行って、話を聞いてみていただきたいと思います。その中で、「行きたい」と思う学校が見つかれば、必ず、お子さんにとって、勉強の動機付けになると思います。
イデア進学ゼミ 塾長日誌 にも続編が掲載されています。ぜひご覧下さい
http://idea.gaias.net/index.html?_startPage=25
勉強方法も大切ですが、一番大切なのは、本人の気持ちだと思います。特に、志望高校が早く決まり、「どうしてもその学校に行きたい。その学校の生徒になっているイメージがつかめている」生徒は、何をするにも意欲が違います。
私は、ぜひ、様々な高校に見学に行くことをおすすめします。それが、行きたくない学校であっても、一度実際に、足を運んで、行ってみることが大切と思います。そうすると、「ここは、合わない。ここには行きたくない」とか、「こんなクラブがあるのか。雰囲気がすごくすてきだ。自分はこの学校に行きたい」などと思うかもしれません。学校の雰囲気とは、恐ろしいもので、空気のように流れているものです。それはうそがつけません。そして、直感的に、合うかどうかもわかったりするのではないでしょうか。
ぜひ、様々な学校に行って、話を聞いてみていただきたいと思います。その中で、「行きたい」と思う学校が見つかれば、必ず、お子さんにとって、勉強の動機付けになると思います。
イデア進学ゼミ 塾長日誌 にも続編が掲載されています。ぜひご覧下さい
http://idea.gaias.net/index.html?_startPage=25
2008年08月14日
夏休みと二学期からの勉強の仕方のアドバイス…家庭学習編
夏休みと二学期からの勉強の仕方のアドバイス
2)自宅での勉強の取り組みの仕方
数学:計算問題では、「2段階の暗算」をなくすことです。2段階の暗算とは、例えば、移行と足し算を同時にするようなことです。こうした、いったん計算した数字を頭に置いて、次の計算を考えてゆく生徒は、計算間違いをよくおこします。間違えるから、余計に、時間もかかり、自信も失い、すべてに悪循環になります。
文章題では、文章を簡単でも絵や図になおして考える癖をつけてみましょう。意外と簡単に、式がわかったりします。
英語:何度も繰り返してほしいのが英単語の復習です。今までに習った単語を、もう一度テストしてみましょう。そして、間違えた単語を、暗記するまで覚えて、5個ずつテストしてゆきましょう。出来れば、2学期に習う単語を5個ずつ暗記してテストしてゆきましょう。忘れてもかまいません。何度でもやり直せばいいんです。そして、教科書の本文を暗記してゆきましょう。その際、声を出して何度も読むだけでも効果があります。英語の力が確実についてゆきます。
イデア進学ゼミ 塾長日誌 にも続編が掲載されています。ぜひご覧下さい
http://idea.gaias.net/index.html?_startPage=25
2)自宅での勉強の取り組みの仕方
数学:計算問題では、「2段階の暗算」をなくすことです。2段階の暗算とは、例えば、移行と足し算を同時にするようなことです。こうした、いったん計算した数字を頭に置いて、次の計算を考えてゆく生徒は、計算間違いをよくおこします。間違えるから、余計に、時間もかかり、自信も失い、すべてに悪循環になります。
文章題では、文章を簡単でも絵や図になおして考える癖をつけてみましょう。意外と簡単に、式がわかったりします。
英語:何度も繰り返してほしいのが英単語の復習です。今までに習った単語を、もう一度テストしてみましょう。そして、間違えた単語を、暗記するまで覚えて、5個ずつテストしてゆきましょう。出来れば、2学期に習う単語を5個ずつ暗記してテストしてゆきましょう。忘れてもかまいません。何度でもやり直せばいいんです。そして、教科書の本文を暗記してゆきましょう。その際、声を出して何度も読むだけでも効果があります。英語の力が確実についてゆきます。
イデア進学ゼミ 塾長日誌 にも続編が掲載されています。ぜひご覧下さい
http://idea.gaias.net/index.html?_startPage=25