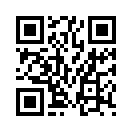2007年10月24日
親と子の関わり−2
問題の半分は自分にも原因があるというところから…
保護者の側や教師の側が、子どもやその周辺に生じる問題について、自分に原因を見つけることは、抵抗を感じる方も多いかもしれませんが、これはとても大切なことだと私は思います。子ども達が荒れている原因が、自分にあるとはなかなか思えないものです。
私たちは、通常、何か問題が起きると人のせいにしがちで、人を責めることで、自分を防御しようとします。しかし、多くの場合、人のせいにして相手を責めても、相手は反発するだけだったという体験はないでしょうか。もちろん、すべてを自分の原因としなくてもかまいませんが、半分は自分にも原因があるというところから考えてみてはいかがでしょうか。自分にも原因があったという気持ちで、子ども達と関わるのと、すべて原因は子どもにあるという気持ちで関わるのとでは、全く違った結果を生むことになると思います。これについては、何度も失敗してきた私の経験から、ぜひおすすめしたいことです。
保護者の側や教師の側が、子どもやその周辺に生じる問題について、自分に原因を見つけることは、抵抗を感じる方も多いかもしれませんが、これはとても大切なことだと私は思います。子ども達が荒れている原因が、自分にあるとはなかなか思えないものです。
私たちは、通常、何か問題が起きると人のせいにしがちで、人を責めることで、自分を防御しようとします。しかし、多くの場合、人のせいにして相手を責めても、相手は反発するだけだったという体験はないでしょうか。もちろん、すべてを自分の原因としなくてもかまいませんが、半分は自分にも原因があるというところから考えてみてはいかがでしょうか。自分にも原因があったという気持ちで、子ども達と関わるのと、すべて原因は子どもにあるという気持ちで関わるのとでは、全く違った結果を生むことになると思います。これについては、何度も失敗してきた私の経験から、ぜひおすすめしたいことです。
2007年10月24日
親と子の関わり−1
子どもと深く出会うと、全く違うその子の姿があらわれてくる
保護者の方から、よく子どもの考えていることがわからない、気持ちが通じ合わないと相談を受けることがあります。中学生にもなると、反抗期もあり、学校での人間関係でかなりのストレスを受けていることも考えられます。
保護者の方にすれば、お子さんのルーズな面や、勉強をしないこと、成績が上がらないことなど、このままでは大変なことになるとの思いから、ついつい言いたくなってしまう。お子さんにすれば、「親は何もわかってくれない」「ああしろ、こうしろと言ってくる。うざい」という感じでしょうか。
もちろん、お子さんにも原因はありますが、保護者の方の気持ちを少し転換することで、お子さんとの関わりは変わってくるように思います。実はこれは教師と生徒との関わりと共通するところがあるように思います。ここで私が提案したいのは、子ども達が荒れているとき、自分の側(保護者や教師の側)の思いとどうつながっているかを考えてみてはいかがでしょうか。そして、子ども達を徹底して受けとめること。その子の痛みや荒れている背景(またはやる気が出ない背景)を感じよう、聴こうとすることです。
私自身は、子ども達と深く出会うこと、その子の人生を丸ごと受けとめようとすることで、全く違うその子の姿があらわれてくる様子を何度も体験してきました。そのように保護者の方にアドバイスして、お子さんとの関わりが転換されたケースを幾度もありました。
現在の子ども達を取り巻く環境は、あまりにも苛酷です。以前と比べることができないほど、情報は溢れ、人間の心の闇が引き出されやすい状況になっています。人間らしく生き生きと生きることが本当に難しくなっているのではないでしょうか。けれども、どの子も本当に素晴らしい可能性と個性の輝きを持っているのも事実です。その子の可能性や輝きをどれほど信じて、受けとめることができるかだと思います。もちろん、是は是、非は非で、言わなければいけないことはありますが、まずは子ども達の友達関係や学校での出来事、背景などを全身を耳にして聞くこと、痛みを共に感じようとするところから、はじめてみることを提案したいと思います。
保護者の方から、よく子どもの考えていることがわからない、気持ちが通じ合わないと相談を受けることがあります。中学生にもなると、反抗期もあり、学校での人間関係でかなりのストレスを受けていることも考えられます。
保護者の方にすれば、お子さんのルーズな面や、勉強をしないこと、成績が上がらないことなど、このままでは大変なことになるとの思いから、ついつい言いたくなってしまう。お子さんにすれば、「親は何もわかってくれない」「ああしろ、こうしろと言ってくる。うざい」という感じでしょうか。
もちろん、お子さんにも原因はありますが、保護者の方の気持ちを少し転換することで、お子さんとの関わりは変わってくるように思います。実はこれは教師と生徒との関わりと共通するところがあるように思います。ここで私が提案したいのは、子ども達が荒れているとき、自分の側(保護者や教師の側)の思いとどうつながっているかを考えてみてはいかがでしょうか。そして、子ども達を徹底して受けとめること。その子の痛みや荒れている背景(またはやる気が出ない背景)を感じよう、聴こうとすることです。
私自身は、子ども達と深く出会うこと、その子の人生を丸ごと受けとめようとすることで、全く違うその子の姿があらわれてくる様子を何度も体験してきました。そのように保護者の方にアドバイスして、お子さんとの関わりが転換されたケースを幾度もありました。
現在の子ども達を取り巻く環境は、あまりにも苛酷です。以前と比べることができないほど、情報は溢れ、人間の心の闇が引き出されやすい状況になっています。人間らしく生き生きと生きることが本当に難しくなっているのではないでしょうか。けれども、どの子も本当に素晴らしい可能性と個性の輝きを持っているのも事実です。その子の可能性や輝きをどれほど信じて、受けとめることができるかだと思います。もちろん、是は是、非は非で、言わなければいけないことはありますが、まずは子ども達の友達関係や学校での出来事、背景などを全身を耳にして聞くこと、痛みを共に感じようとするところから、はじめてみることを提案したいと思います。
2007年07月22日
よくある質問3
Q 理科や社会が苦手です。どうすれば伸びるようになるでしょうか……
A 小学校も5年生くらいになると、子どもたちは非常に重要な理科や社会の単元を学校で習います。そして、あっという間にその重要な単元を習い終えてしまうのです。理科や社会は興味のある子には何もしなくても点数をとってしまいますが、興味を持てない子には、中学校になってますます嫌いになってしまうようです。小学校と中学校の教科書を見比べてみても、ポイントはほとんど同じです。小学校で重要なことは、中学校では超重要事項として教科書に出ていることが多いようです。
ですから、小学校の4年から6年くらいの時期に、どれだけ理科や社会に興味を持つかで、中学生になって大きな分かれ道になると思います。
では、どのようにすればいいのでしょうか。私は、「学習漫画」をおすすめしています。学研のひみつシリーズや、歴史の漫画、ドラえもんの学習漫画など、さまざまに本屋さんで売られています。このようなものこそ、この時期に読むのが最適です。
この時、少しひと工夫が必要です。お子さんに「これを読みなさい」と言うと、また押し付けや義務になって、漫画すらも「勉強」になってしまう可能性があります。ですから、何も言わずに、適当なものを購入して、さりげなくリビングにでも置いておくのです。何日かたって、お子さんが読み出したらしめたもの。その時こそ、お子さんが「自分の意思」で「興味を持って学び始めた」ということになるのではないかと思います。
勉強も興味から入ってゆくと感動や、発見があるのでなかなか忘れるものではありません。それに、漫画による視覚から入ったものは、記憶に残りやすいものです。歴史上の人物でも、写真や漫画で顔を知っていたら、中学で学んだ時に、即座に顔が思い浮かべられ、学校の授業を聞いているときも、その映像を浮かべながら話を聞くことになるでしょう。実際、歴史が好きで仕方がないという生徒は、ほとんど小学生の時期に人物像を漫画や図鑑で見たことがあり、とても馴染みのあるものであることが多いのです。
もう一つ、付加えておくと、歴史漫画は、いくつかの出版社から出ていますが、できれば、人物の特徴がはっきりしていて、区別しやすい絵を描かれる漫画家のものがよいと思います。同じような顔ばかりが出てくるようでは、子どもたちはますます混乱するだけになるかも知れないからです。
そして、決して「読みなさい」と言わないこと。子ども達には、どの子も「学びたい」という気持ちが強くあります。それを信じて、一度試してみていただければと思います。
A 小学校も5年生くらいになると、子どもたちは非常に重要な理科や社会の単元を学校で習います。そして、あっという間にその重要な単元を習い終えてしまうのです。理科や社会は興味のある子には何もしなくても点数をとってしまいますが、興味を持てない子には、中学校になってますます嫌いになってしまうようです。小学校と中学校の教科書を見比べてみても、ポイントはほとんど同じです。小学校で重要なことは、中学校では超重要事項として教科書に出ていることが多いようです。
ですから、小学校の4年から6年くらいの時期に、どれだけ理科や社会に興味を持つかで、中学生になって大きな分かれ道になると思います。
では、どのようにすればいいのでしょうか。私は、「学習漫画」をおすすめしています。学研のひみつシリーズや、歴史の漫画、ドラえもんの学習漫画など、さまざまに本屋さんで売られています。このようなものこそ、この時期に読むのが最適です。
この時、少しひと工夫が必要です。お子さんに「これを読みなさい」と言うと、また押し付けや義務になって、漫画すらも「勉強」になってしまう可能性があります。ですから、何も言わずに、適当なものを購入して、さりげなくリビングにでも置いておくのです。何日かたって、お子さんが読み出したらしめたもの。その時こそ、お子さんが「自分の意思」で「興味を持って学び始めた」ということになるのではないかと思います。
勉強も興味から入ってゆくと感動や、発見があるのでなかなか忘れるものではありません。それに、漫画による視覚から入ったものは、記憶に残りやすいものです。歴史上の人物でも、写真や漫画で顔を知っていたら、中学で学んだ時に、即座に顔が思い浮かべられ、学校の授業を聞いているときも、その映像を浮かべながら話を聞くことになるでしょう。実際、歴史が好きで仕方がないという生徒は、ほとんど小学生の時期に人物像を漫画や図鑑で見たことがあり、とても馴染みのあるものであることが多いのです。
もう一つ、付加えておくと、歴史漫画は、いくつかの出版社から出ていますが、できれば、人物の特徴がはっきりしていて、区別しやすい絵を描かれる漫画家のものがよいと思います。同じような顔ばかりが出てくるようでは、子どもたちはますます混乱するだけになるかも知れないからです。
そして、決して「読みなさい」と言わないこと。子ども達には、どの子も「学びたい」という気持ちが強くあります。それを信じて、一度試してみていただければと思います。
2007年06月21日
よくある質問2
Q テストの結果を全然見せてくれません。どうせ悪いから見せてくれないのだと思うのですが……
A 中学1年生の最初の頃は、点数もよくて、お母さんに点数を見せてもらっていたのが、中1も後半くらいになると、点数が思うように取れずに、親に見せないお子さんが増えてきます。子どもたちはみんなご両親に認めてもらいたい、ほめてもらいたいと思っていますので、叱られると思うと見せたくないと思うのではないでしょうか。
点数の良し悪しにこだわりすぎるのもどうかと思います。それよりも、テストに対して一緒に後智慧することをおすすめします。後智慧とは、テストの振り返りをして、どう思ったか、良かった点はどんなところか、足りなかった点はどんなところか。などを振り返り、具体的に、次回どのように向かうかを考えてみることを言います。
そして、「あなたが毎日勉強していないからだ」とは決して言わないで、「次からこのようにがんばる」とお子さんが言われたら、「わかった」と言って、励まして差し上げてください。そして、具体的に「もし、もう一度テストを受けなおせるとしたら、どんな風に取り組む?」と聞いてあげるのもいいと思います。
勉強面もそうですが、お子さんのライフスタイルを転換してもらうチャンスの時です。どんなことでもいい、お子さんが一つでも自分の口からこのようにすると言ってもらうことがとても大切です。
「テスト1週間前になったらテレビを1時間に減らす」とか「1週間前までに学校の問題集を1冊は仕上げる」とか、「1週間前からは携帯電話をさわらない」など、どんな些細なことでもいいから変えれそうな「宣言」を一つしていただくのです。宣言をすることで、お子さんに大きな転換が訪れてゆくと思います。お子さんに変われるという自信が生まれれば、きっとテストもお母さんに見せていただけるようになると思います。
A 中学1年生の最初の頃は、点数もよくて、お母さんに点数を見せてもらっていたのが、中1も後半くらいになると、点数が思うように取れずに、親に見せないお子さんが増えてきます。子どもたちはみんなご両親に認めてもらいたい、ほめてもらいたいと思っていますので、叱られると思うと見せたくないと思うのではないでしょうか。
点数の良し悪しにこだわりすぎるのもどうかと思います。それよりも、テストに対して一緒に後智慧することをおすすめします。後智慧とは、テストの振り返りをして、どう思ったか、良かった点はどんなところか、足りなかった点はどんなところか。などを振り返り、具体的に、次回どのように向かうかを考えてみることを言います。
そして、「あなたが毎日勉強していないからだ」とは決して言わないで、「次からこのようにがんばる」とお子さんが言われたら、「わかった」と言って、励まして差し上げてください。そして、具体的に「もし、もう一度テストを受けなおせるとしたら、どんな風に取り組む?」と聞いてあげるのもいいと思います。
勉強面もそうですが、お子さんのライフスタイルを転換してもらうチャンスの時です。どんなことでもいい、お子さんが一つでも自分の口からこのようにすると言ってもらうことがとても大切です。
「テスト1週間前になったらテレビを1時間に減らす」とか「1週間前までに学校の問題集を1冊は仕上げる」とか、「1週間前からは携帯電話をさわらない」など、どんな些細なことでもいいから変えれそうな「宣言」を一つしていただくのです。宣言をすることで、お子さんに大きな転換が訪れてゆくと思います。お子さんに変われるという自信が生まれれば、きっとテストもお母さんに見せていただけるようになると思います。
2007年06月18日
よくある質問1
Q 中学になっても家で勉強する姿を見たことがないのですが、家でどのように声をかけたらいいでしょうか
A 「勉強しなさい」とお母さんに言われて、お子さんが自分の部屋に行く。そっとのぞいてみると漫画を読んでいたり、ゲームをしている。あるいは部屋にも行かないで、ずっとテレビを夢中になって見ている。また、一言注意すると「今、やろうと思ったのに、やる気をなくした」と言われる。このような光景は良くあるかもしれません。
ただ、ご家族ができることとして、環境を整えてあげることができると思います。子どもにとって、家族の方がテレビを見たり、ゲームをしていると勉強する気になかなかなれないものでしょう。テレビを消す時間帯を作り、家族で本を読むとか、何かの勉強をされるとかするのはどうでしょうか。そして、勉強は子ども部屋でするのではなく、お母さんの目の届くところでしてもらうのも良いと思います。
また、中3生であるならば、行きたい学校を決めて、志望校見学に行くのもとてもよいと思います。
子ども達にとって、高校受験はとても先に見えています。けれども、学校見学などをして、「ここに行きたい」と強く思うと、今までに見たことのないお子さんの姿が現れたりします。
また、志望校の過去の問題集を買いに行くなど、受験を目の前に引き寄せると、切実感が出てきます。ぜひ、家族ができる協力を考えていただければと思います。
A 「勉強しなさい」とお母さんに言われて、お子さんが自分の部屋に行く。そっとのぞいてみると漫画を読んでいたり、ゲームをしている。あるいは部屋にも行かないで、ずっとテレビを夢中になって見ている。また、一言注意すると「今、やろうと思ったのに、やる気をなくした」と言われる。このような光景は良くあるかもしれません。
ただ、ご家族ができることとして、環境を整えてあげることができると思います。子どもにとって、家族の方がテレビを見たり、ゲームをしていると勉強する気になかなかなれないものでしょう。テレビを消す時間帯を作り、家族で本を読むとか、何かの勉強をされるとかするのはどうでしょうか。そして、勉強は子ども部屋でするのではなく、お母さんの目の届くところでしてもらうのも良いと思います。
また、中3生であるならば、行きたい学校を決めて、志望校見学に行くのもとてもよいと思います。
子ども達にとって、高校受験はとても先に見えています。けれども、学校見学などをして、「ここに行きたい」と強く思うと、今までに見たことのないお子さんの姿が現れたりします。
また、志望校の過去の問題集を買いに行くなど、受験を目の前に引き寄せると、切実感が出てきます。ぜひ、家族ができる協力を考えていただければと思います。
2007年06月08日
10分間読書&国語読解の成果
10分間読書&国語読解の成果
国語の音読が大の苦手だったという小学2年生の生徒さんが、スラスラ音読ができるようになっています。算数の文章問題を絵や図を使って解くことで、逆に国語力がついてゆくのは当塾の特徴的な現象です。
今まであれほど勉強がきらいだった小学4年生の生徒さんが、夜、寝る前に1時間も読書するようになったという喜びの声もいただいています。
国語の音読が大の苦手だったという小学2年生の生徒さんが、スラスラ音読ができるようになっています。算数の文章問題を絵や図を使って解くことで、逆に国語力がついてゆくのは当塾の特徴的な現象です。
今まであれほど勉強がきらいだった小学4年生の生徒さんが、夜、寝る前に1時間も読書するようになったという喜びの声もいただいています。
2007年06月06日
イデア式算数文章題の成果
イデア式算数文章題の成果
現在、小学2年から6年までの子ども達が、複雑な算数文章問題を絵や図や表を駆使して、問題に取り組まれています。
特に最近、驚きを隠せないのが、家での勉強量の多さです。当塾では、「次の塾までにプリント3枚または3ページはやってこようね」というだけですが、多くの子ども達が、8ページ以上をしてこられます。中には40ページ以上する生徒もいます。
塾では一切、強制しない。押し付けもしない。なのに、子ども達は意欲を持って勉強をしてくるのです。さらに塾では、学校で習うような勉強の仕方はしません。もっぱら、見たこともない算数文章問題やパズル、さらに国語の読解問題をして、頭の鍛錬を中心にしています。
けれども、こうした鍛錬で、子ども達は、頭を使うことが好きになります。1時間もかけて解けたときの喜びは、快感だという生徒もいます。中には、1週間かけて1問を解く生徒もいます。「友達同士で、一緒に塾の宿題をするのだと言ってずっと勉強するようになったのです。それも本当に楽しそうだ。」と驚かれるお母さんが増えています。
現在、小学2年から6年までの子ども達が、複雑な算数文章問題を絵や図や表を駆使して、問題に取り組まれています。
特に最近、驚きを隠せないのが、家での勉強量の多さです。当塾では、「次の塾までにプリント3枚または3ページはやってこようね」というだけですが、多くの子ども達が、8ページ以上をしてこられます。中には40ページ以上する生徒もいます。
塾では一切、強制しない。押し付けもしない。なのに、子ども達は意欲を持って勉強をしてくるのです。さらに塾では、学校で習うような勉強の仕方はしません。もっぱら、見たこともない算数文章問題やパズル、さらに国語の読解問題をして、頭の鍛錬を中心にしています。
けれども、こうした鍛錬で、子ども達は、頭を使うことが好きになります。1時間もかけて解けたときの喜びは、快感だという生徒もいます。中には、1週間かけて1問を解く生徒もいます。「友達同士で、一緒に塾の宿題をするのだと言ってずっと勉強するようになったのです。それも本当に楽しそうだ。」と驚かれるお母さんが増えています。
2007年05月30日
家族で蛍を見に行きました
家族で蛍を見に行きました。
毎年、この時期になると、家族で蛍を見に行きます。
場所は、兵庫県川辺郡の山の中。
今年は4月に雨が少なかったので、蛍が出るのが遅いそうで、あと1週間か10日ほど先がピークではないかとのことでした。
時間は夜8時前後。お月様が出ている時は、あまり蛍が上空にあがってこないのだそうです。
蛍達は月明かりで、用心しているのでしょうか。ベストは、雨が降った後の曇り空の夜。
そしてあまり寒くない夜がいいようです。
昨年は、ちょうど、こうした条件がぴったり重なった時に、見にいくことができ、蛍の乱舞が見ることができました。ものすごく幻想的でした。
今年もどこから聞いたのか、多くの方々も見に来られていました。
あとから聞いた話では、500メートルから1キロの範囲に2000匹ほどの蛍がいたそうです。
地元の農家の方もとても親切で、いろいろ説明してくださいます。
こんな蛍が住める場所がどんどん少なくなってゆくことを思うとき、何としても美しい地球を取り戻したいと願うばかりでした。
日本全国、さまざまに蛍が見られるスポットがあります。インターネットでも探せますので、ぜひ子ども達を連れて見に行かれてはいかがでしょうか。
毎年、この時期になると、家族で蛍を見に行きます。
場所は、兵庫県川辺郡の山の中。
今年は4月に雨が少なかったので、蛍が出るのが遅いそうで、あと1週間か10日ほど先がピークではないかとのことでした。
時間は夜8時前後。お月様が出ている時は、あまり蛍が上空にあがってこないのだそうです。
蛍達は月明かりで、用心しているのでしょうか。ベストは、雨が降った後の曇り空の夜。
そしてあまり寒くない夜がいいようです。
昨年は、ちょうど、こうした条件がぴったり重なった時に、見にいくことができ、蛍の乱舞が見ることができました。ものすごく幻想的でした。
今年もどこから聞いたのか、多くの方々も見に来られていました。
あとから聞いた話では、500メートルから1キロの範囲に2000匹ほどの蛍がいたそうです。
地元の農家の方もとても親切で、いろいろ説明してくださいます。
こんな蛍が住める場所がどんどん少なくなってゆくことを思うとき、何としても美しい地球を取り戻したいと願うばかりでした。
日本全国、さまざまに蛍が見られるスポットがあります。インターネットでも探せますので、ぜひ子ども達を連れて見に行かれてはいかがでしょうか。
2007年05月29日
懇談のタイミング
懇談のタイミング
新しく入塾された子ども達が塾に入ってから2〜3カ月も過ぎると、子ども達は様々な顔を見せてくれます。
私達が理解に苦しむ行動や発言をする子どももいれば、なかなか心を開いてくれなかったりする場合もあります。こんな時、私は懇談のチャンスと思って、保護者の方との個人懇談をさせていただきます。
その生徒の幼い頃からの話を聞かせていただくのです。すると、なぜそうした行動をとるのか、その生徒の心の痛みがわかってきます。
「そんな痛みをこの子は持っていたのかと思うとき、何もわからずに表面的に出会っていたことを申し訳なく思います。けれども、そんな子ども達の痛みをお母さん方から教えていただくことは、何にもまして有難いことと思っています。
そうした懇談の後、子ども達の勉強に向かう姿勢や私達との関わり等、すべてにおいて不思議と変化しているのです。教師の仕事とは、どれだけ子ども達の抱える痛みを自分の心に引き寄せられるかということかもしれないと思うこの頃です。
新しく入塾された子ども達が塾に入ってから2〜3カ月も過ぎると、子ども達は様々な顔を見せてくれます。
私達が理解に苦しむ行動や発言をする子どももいれば、なかなか心を開いてくれなかったりする場合もあります。こんな時、私は懇談のチャンスと思って、保護者の方との個人懇談をさせていただきます。
その生徒の幼い頃からの話を聞かせていただくのです。すると、なぜそうした行動をとるのか、その生徒の心の痛みがわかってきます。
「そんな痛みをこの子は持っていたのかと思うとき、何もわからずに表面的に出会っていたことを申し訳なく思います。けれども、そんな子ども達の痛みをお母さん方から教えていただくことは、何にもまして有難いことと思っています。
そうした懇談の後、子ども達の勉強に向かう姿勢や私達との関わり等、すべてにおいて不思議と変化しているのです。教師の仕事とは、どれだけ子ども達の抱える痛みを自分の心に引き寄せられるかということかもしれないと思うこの頃です。
2007年05月10日
受けとめに80パーセント
受けとめに80パーセント
わが子が、学校でいじめにあっている。遊んでばかりで全く勉強しない。進路のことで悩んでいる。反抗ばかりして困る。クラブ、勉強、友達関係に悩んでいる。など、子ども達が何かに行き詰ったとき、どうされるでしょうか。
とかく私達大人は「ああしなさい、こうしなさい」と指示したり、説得しようとしがちです。
けれども、それでは、反発を生んだり、子ども達のエネルギーが失われてしまったりするのではないでしょうか。
私は、ぜひ、周囲の大人たちが子ども達の気持ちを「受けとめる」ことをして頂きたいと思います。
それも、すぐに言いたくなる気持ちを抑えて、最後まで子どもの気持ちを受けとめるのです。
どの子も、受けとめてほしいのです。
そして、自分の気持ちを整理したがっています。
そして、できれば出てきた気持ちを書いてみましょう。様々な痛みを持っていて、心はずたずたになっているかもしれません。
そんな子ども達の痛みや苦しみを少しでも感じることができ、子ども達が気持ちを整理することができれば、大きな解決の糸口が生まれてくるに違いありません。
お子さんが話しているときは、「絶対、口を挟まない。」ことを原則に、お子さんの痛みが何なのか、深く感じながら話を聞かれるのが良いと思います。
子ども達の悲痛な叫びともいえる言葉を聞けたとき、その奥に、その子の輝く何かを同時に見えるに違いありません。
「受けとめに80%のエネルギーを使う」……これを目標に、ぜひお子さんのお気持ちを聞いてあげてください。(これは私自身の目標でもあります)
わが子が、学校でいじめにあっている。遊んでばかりで全く勉強しない。進路のことで悩んでいる。反抗ばかりして困る。クラブ、勉強、友達関係に悩んでいる。など、子ども達が何かに行き詰ったとき、どうされるでしょうか。
とかく私達大人は「ああしなさい、こうしなさい」と指示したり、説得しようとしがちです。
けれども、それでは、反発を生んだり、子ども達のエネルギーが失われてしまったりするのではないでしょうか。
私は、ぜひ、周囲の大人たちが子ども達の気持ちを「受けとめる」ことをして頂きたいと思います。
それも、すぐに言いたくなる気持ちを抑えて、最後まで子どもの気持ちを受けとめるのです。
どの子も、受けとめてほしいのです。
そして、自分の気持ちを整理したがっています。
そして、できれば出てきた気持ちを書いてみましょう。様々な痛みを持っていて、心はずたずたになっているかもしれません。
そんな子ども達の痛みや苦しみを少しでも感じることができ、子ども達が気持ちを整理することができれば、大きな解決の糸口が生まれてくるに違いありません。
お子さんが話しているときは、「絶対、口を挟まない。」ことを原則に、お子さんの痛みが何なのか、深く感じながら話を聞かれるのが良いと思います。
子ども達の悲痛な叫びともいえる言葉を聞けたとき、その奥に、その子の輝く何かを同時に見えるに違いありません。
「受けとめに80%のエネルギーを使う」……これを目標に、ぜひお子さんのお気持ちを聞いてあげてください。(これは私自身の目標でもあります)